二十四節気、七十二候、五節句、節供、雑節などの暦に沿って季節を感じられるよう、それぞれの記事をカレンダーとしてまとめてみました。常に季節を感じながら、自分らしい時間を過ごすことができたら、幸せなことなのかと思っております。
◆は毎年日にちが変動する行事です。暦の日にちは、その年により変わるものもございますので、ご注意ください。
- 春の暦
- ◆2026年2月4日~18日 二十四節気 「立春」
- ◆2026年2月19日~3月4日 二十四節気 「雨水」
- 2026年2月23日 富士山の日
- 2026年3月3日 五節句 「上巳の節句」 、 節供 「上巳の草餅」
- ◆2026年3月5日~19日 二十四節気 「啓蟄」
- ◆2026年3月17日~23日 中日20日 雑節 「春彼岸」
- ◆2026年3月20日~4月4日 二十四節気 「春分」
- ◆2026年3月25日 雑節 「春社日」
- ◆2026年4月5日~19日 二十四節気 「清明」
- ◆2026年4月17日~5月4日 雑節 「春土用 」
- ◆2026年4月20日~5月4日 二十四節気 「穀雨」
- ◆2026年5月2日 雑節 「八十八夜」
- ◆2026年5月4日 雑節 「節分」
- 夏の暦
- 2026年5月5日 五節句 「端午の節句」 、 節供 「端午の粽」
- ◆2026年5月5日~20日 二十四節気 「立夏」
- ◆2026年5月21日~6月5日 二十四節気 「小満」
- ◆2026年6月6日~20日 二十四節気 「芒種」
- ◆2026年6月11日 雑節「入梅」
- 2026年6月16日 嘉祥の日
- ◆2026年6月21日~7月6日 二十四節気 「夏至」
- 2026年6月30日 夏越の大祓
- ◆2026年7月2日 雑節 「半夏生」
- 2026年7月7日 五節句「七夕」、節供 「七夕の索餅」
- ◆2026年7月7日~22日 二十四節気 「小暑」
- ◆2026年7月20日~8月6日 雑節「夏土用」
- ◆2026年7月23日~8月6日 二十四節気 「大暑」
- ◆2026年8月6日 雑節 「節分」
- 秋の暦
- ◆2026年8月7日~22日 二十四節気 「立秋」
- ◆2026年8月23日~9月6日 二十四節気 「処暑」
- ◆2026年9月1日 雑節 「二百十日」
- ◆2026年9月7日~22日 二十四節気 「白露」
- 2026年9月9日 五節句 「重陽の節句」 、節供「栗の節供」
- ◆2026年9月11日 雑節 「二百二十日」
- ◆2026年9月20日~26日 中日23日 雑節 「秋彼岸」
- ◆2026年9月22日 雑節 「秋社日」
- ◆2026年9月23日~10月7日 二十四節気 「秋分」
- ◆2026年9月25日 「十五夜」
- ◆2026年10月8日~22日 二十四節気 「寒露」
- ◆2026年10月20日~11月6日 雑節 「秋土用」
- ◆2026年10月23日~11月6日 二十四節気 「霜降」
- ◆2026年10月23日 「十三夜」
- ◆2026年11月6日 雑節 「節分」
- 冬の暦
- ◆2026年11月7日~21日 二十四節気 「立冬」
- ◆2026年11月9日 節供 「亥の子餅」
- ◆2026年11月22日~12月6日 二十四節気 「小雪」
- 2026年11月23日 新嘗祭(勤労感謝の日)
- ◆2026年12月7日~21日 二十四節気 「大雪」
- お正月のスケジュール
- 2026年12月13日 正月事始め
- ◆2026年12月22日~2027年1月4日 二十四節気 「冬至」
- 冬至に食べる「冬の七草」
- 2027年1月1日 節供 「元旦の膳(おせち)」
- ◆2027年1月5日~19日 二十四節気 「小寒」
- 2027年1月7日 五節句 「人日の節句」
- 2027年1月11日「 鏡開き」
- 2027年1月15日 節供 「上元の粥」、「小正月」
- ◆2027年1月17日~2月3日 雑節 「冬土用」
- ◆2027年1月20日~2月3日 二十四節気 「大寒」
- ◆2027年2月3日 雑節 「節分」
- 暦とは
- しつらえとは
- 夏にしつらえるものについて
- 明日はどんな手仕事する?
- 季節の手仕事の関連記事
春の暦
◆2026年2月4日~18日 二十四節気 「立春」

◆2026年2月19日~3月4日 二十四節気 「雨水」

2026年2月23日 富士山の日


2026年3月3日 五節句 「上巳の節句」 、 節供 「上巳の草餅」


◆2026年3月5日~19日 二十四節気 「啓蟄」

◆2026年3月17日~23日 中日20日 雑節 「春彼岸」

◆2026年3月20日~4月4日 二十四節気 「春分」

◆2026年3月25日 雑節 「春社日」

◆2026年4月5日~19日 二十四節気 「清明」

◆2026年4月17日~5月4日 雑節 「春土用 」

◆2026年4月20日~5月4日 二十四節気 「穀雨」

◆2026年5月2日 雑節 「八十八夜」
雑節のひとつで、立春から数えて88日目のことをいいます。
もう霜が降りる心配がないとされ、作物の種蒔きや野菜の植え替え、茶摘みなどを始めるのに最適な時期とされます。
この日から6月にかけて、みずみずしい新芽を摘んで作られるお茶のことを「新茶」と言います。中でも、「八十八夜」当日に摘まれた新茶を飲むと病気にかからない、長生きできると言い伝えられ、縁起物として大変珍重されました。
◆2026年5月4日 雑節 「節分」
「節分」とは、「季節を分ける」ことです。暦の上での季節の始まりの前の日のことを「節分」といいます。節分は1年に4回あります。立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前の日のことをいいます。春が終わり、夏が始まる「節分」です。
夏の暦
2026年5月5日 五節句 「端午の節句」 、 節供 「端午の粽」

◆2026年5月5日~20日 二十四節気 「立夏」

◆2026年5月21日~6月5日 二十四節気 「小満」

◆2026年6月6日~20日 二十四節気 「芒種」

◆2026年6月11日 雑節「入梅」
「入梅」は、雑節のひとつ。梅雨に入る時期ということです。
農家さんにとっては、梅雨入りの時期を知ることは、田植えの日取りを決めるのに重要でした。
漬けた青梅が漬かり始める頃、そして熟した黄梅で梅干しを漬ける頃になります。

雨の日を楽しむために、傘やレインコート、レインシューズや長靴などを準備しましょう。お気に入りのものがあると、使いたくなって雨の日がくるのが嬉しくなります。
2026年6月16日 嘉祥の日

◆2026年6月21日~7月6日 二十四節気 「夏至」

2026年6月30日 夏越の大祓

◆2026年7月2日 雑節 「半夏生」

2026年7月7日 五節句「七夕」、節供 「七夕の索餅」

◆2026年7月7日~22日 二十四節気 「小暑」

◆2026年7月20日~8月6日 雑節「夏土用」

◆2026年7月23日~8月6日 二十四節気 「大暑」

◆2026年8月6日 雑節 「節分」
「節分」とは、「季節を分ける」ことです。暦の上での季節の始まりの前の日のことを「節分」といいます。節分は1年に4回あります。立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前の日のことをいいます。夏が終わり、秋が始まる「節分」です。
秋の暦
◆2026年8月7日~22日 二十四節気 「立秋」

◆2026年8月23日~9月6日 二十四節気 「処暑」

◆2026年9月1日 雑節 「二百十日」
◆2026年9月7日~22日 二十四節気 「白露」

2026年9月9日 五節句 「重陽の節句」 、節供「栗の節供」

◆2026年9月11日 雑節 「二百二十日」
◆2026年9月20日~26日 中日23日 雑節 「秋彼岸」

◆2026年9月22日 雑節 「秋社日」

◆2026年9月23日~10月7日 二十四節気 「秋分」

◆2026年9月25日 「十五夜」

◆2026年10月8日~22日 二十四節気 「寒露」

◆2026年10月20日~11月6日 雑節 「秋土用」

◆2026年10月23日~11月6日 二十四節気 「霜降」

◆2026年10月23日 「十三夜」

◆2026年11月6日 雑節 「節分」
「節分」とは、「季節を分ける」ことです。暦の上での季節の始まりの前の日のことを「節分」といいます。節分は1年に4回あります。立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前の日のことをいいます。秋が終わり、冬が始まる「節分」です。
冬の暦
◆2026年11月7日~21日 二十四節気 「立冬」

◆2026年11月9日 節供 「亥の子餅」

◆2026年11月22日~12月6日 二十四節気 「小雪」

2026年11月23日 新嘗祭(勤労感謝の日)

新嘗祭(にいなめさい)とは、その年に収穫されたものを神に供えて感謝をする行事です。
三嶋大社では、写真のように、宝物殿に三島で採れた野菜たちが捧げられます。
◆2026年12月7日~21日 二十四節気 「大雪」

お正月のスケジュール

2026年12月13日 正月事始め




◆2026年12月22日~2027年1月4日 二十四節気 「冬至」

冬至に食べる「冬の七草」

2027年1月1日 節供 「元旦の膳(おせち)」



◆2027年1月5日~19日 二十四節気 「小寒」

2027年1月7日 五節句 「人日の節句」
新しい年を迎え、松の内の間は、神のための日とされ、7日から人の日が始まるとされていました。人日の節句は、五節句の一つです。七草粥を食べ、お正月料理で疲れた胃腸を休め、平常の食生活に戻す区切りとします。

2027年1月11日「 鏡開き」

2027年1月15日 節供 「上元の粥」、「小正月」


◆2027年1月17日~2月3日 雑節 「冬土用」

◆2027年1月20日~2月3日 二十四節気 「大寒」

◆2027年2月3日 雑節 「節分」
「節分」とは、「季節を分ける」ことです。暦の上での季節の始まりの前の日のことを「節分」といいます。節分は1年に4回あります。立春、立夏、立秋、立冬のそれぞれの前の日のことをいいます。冬が終わり、新しい年の春が始まる「節分」です。



暦とは
暦とは、年月を定める方法のしくみで、節気や行事などで分類されています。
二十四節気とは
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽年を太陽の黄経に従って24等分して、季節の指標となるのに用いる語になります。中国より伝わったもので、その等分点を名付けているのが、この二十四節気です。
暦の上での四季は、これで分けられています。
二十四節気は、月の満ち欠けに応じて日にちが変わるため、節気の第1日目の日にちがその年により前後します。
1つの節気は、約15日間です。
「立春」「立夏」「立秋」「立冬」は、「四立(しりゅう)」と呼ばれ、季節の始まりとなります。
日照時間が最も長い「夏至」、日照時間が最も短い「冬至」、昼と夜の長さが同じになる「春分」と「秋分」は、「二至二分(にしにぶん)」と呼ばれ、それぞれの季節の真ん中になります。
七十二候とは
七十二候(しちじゅうにこう)とは、中国で考案されたものを、江戸時代に日本に合わせて作り変えられたものです。旧暦で1年を72に分けた5日間または6日間を1候とし、その時候の天気や動物の生態の微妙な変化、花の咲く時期などをより具体的示したものです。季節の移り変わりと上手に付き合いながら暮らす様が、それぞれの言葉に著されています。
地球温暖化により、多少のずれは感じられることもありますが、ほぼその時期にその事が起きる七十二候は、季節を気が付かせてくれる「季節のお知らせ」とでもいうのでしょうか。
七十二候は、二十四節気の記事の中に、初候、次候、末候に分け、短文で表現されているものを記載しております。意味不明な昔ながらの表現を、今風に解釈したりしております。ご了承ください。
五節句とは
季節の変わり目に無病息災や豊作、子孫繁栄を願って邪気を祓う行事のことです。中国より伝わったもので、5つになったのは、江戸時代になってからになります。
節供(せちく)とは
節日と言われる上巳の節句や端午の節句などの五節句の際に、神様に供えられたお料理のことをいいます。正式には、供御(くご・天皇の飲食物)のことをいいます。せく、おせち、せちごとなどともいいます。
この節供を「御節供(おせちく)料理」といっていたが、のちに節会のうちでも重要な正月の祝い膳のことを「おせち料理」というようになったといわれています。
雑節とは
二十四節気と同様に季節の節目を表す語です。農業や生活の目安として定められました。
しつらえとは
お花のお稽古をしていても、「しつらえ」って何?と聞かれることがよくあります。
「しつらえ」とは、平安時代、客を招いての宴などのハレの儀式の日に、寝殿(主人の住まい)の母屋(柱など組み立て部分)および廂(ひさし)に調度を立て、室内を几帳(きちょう)や屏風、置畳などで装飾したことをいいました。 調度品を替えるなどといいます。
「しつらえ」とは、「設え」「室礼」「鋪設」「補理」といった字をあてたりします。もうける、そなえる、ととのえる、そのために作る、つくり足すということです。
みなさんが、「しつらえ」というと、季節に合わせて室内装飾をするとか、インテリアを素敵にするとか、家具を新しくするなどという方が多い気がします。確かに間違いではありません。もともとは、お客様が来られる際や、季節が変わるごとにその季節に合わせて部屋の装飾を変えたというものなので、それももちろん良いと思います。
ただ、私の思う現代でいう「しつらえ」とは、ただ単に装飾をするということではなく、それらすべての行為に対しての感謝の気持ちを表した見えぬ想いともいえるのではないでしょうか。
日本語特有の奥深い「しつらえ」という言葉、そこには、答えがあるような、ないような…。深く考えさせられる素敵な言葉であるような気もします。
この「暦としつらえの季節の手仕事」の記事の中にも、それぞれの季節の「しつらえ」を書かせていただいております。どうしても、基本の季節の行事の「しつらえ」が多くなってしまいますが、どれが正しくて、どれが間違いということはなく、自身が日々過ごしていく上で、心地が良い空間であればそれはそれでよいのではないかと思っております。心穏やかに…
夏にしつらえるものについて
あいうえお順に並べてあります。
すだれ 簾
「すだれ」についてはこちら ↓↓↓

たたみ 畳
「たたみ」についてはこちら ↓↓↓
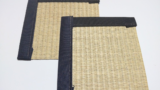
明日はどんな手仕事する?
「旬のものを食べていると病気知らず」なんてことを言います。冷蔵庫も冷凍庫もなかった時代には、その日に採れたものを食べたり、長期保存する方法があったり…旬のものは、その時に食べていました。今では、ハウス栽培もあり、旬がいつなのかわからなくなってしまうくらい、年中欲しいものが手に入るようになりました。それが悪いと言っている訳ではなく、なんとなく物悲しさを感じます。
常に食べられるものを、常に食べている。そんな狭い世界を勿体ないと思うようになりました。季節のものを季節に食すこと、それは、美味しいものを美味しい時期に食す、何でもないことなのです。しかし今では、それが贅沢なことになってしまっています。
暦を知ることで、季節の移り変わりが見えてきます。その変わっていく様を感じていただけるよう、1年に渡って、記録をしています。気候が温かい静岡の記録のため、寒い地域の方には、参考にならないかもしれませんが、お付き合いいただけると幸いです。
それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓







