小満とは
「小満」とは、二十四節気のひとつです。
ようやく暑さが加わり、麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけはじめ、万物が満つる頃という意味です。
田の苗が育ち始めるころが、麦にとっての秋になります。黄色の麦の穂が一面に続く「麦秋」は、ちょうど梅雨に入る少し前の5月末ごろです。黄色の麦の色とは対照的に、周りには、緑の草木や稲が伸びていく時期になります。この麦秋の小満から夏土用(7月末)までが農作業の一区切りとなります。
二十四節気(にじゅうしせっき)とは
二十四節気(にじゅうしせっき)は、太陽年を太陽の黄経に従って24等分して、季節の指標となるのに用いる語になります。中国より伝わったもので、その等分点を名付けているのが、この二十四節気です。
暦の上での四季は、これで分けられています。
二十四節気は、月の満ち欠けに応じて日にちが変わるため、節気の第1日目の日にちがその年により前後します。
1つの節気は、約15日間です。
小満の七十二候
七十二候(しちじゅうにこう)とは
七十二候(しちじゅうにこう)とは、元々中国で考案されたものを、江戸時代に日本に合わせて作り変えられたものです。旧暦で1年を72に分けた5日間または6日間を1候とし、その時候の天気や動植物の生態の微妙な変化を示したものです。季節と上手に付き合いながら暮らす様が、それぞれの言葉に著されています。
地球温暖化により、多少のずれは感じられることもありますが、ほぼその時期にその事が起きる七十二候は、季節を気が付かせてくれる「季節のお知らせ」とでもいうのでしょうか。
初候「蚕起食桑(かいこおこってくわをくらう)」5月21日~25日
蚕が桑を盛んに食べ始める頃です。
次候「紅花栄(こうかさかう)」5月26日~30日
紅花が盛んに咲く頃です。
末候「麦秋至(ばくしゅういたる)」5月31日~6月5日
麦が熟し麦の収穫が行われる頃です。
小満の頃のしつらえ「たたみ」
「たたみ」をしつらえるのに時期は関係ありませんが、近年では、夏に涼を求めてたたみ製品を使う方が増えているため、ここに記させていただきました。
「畳」についてはこちら ↓↓↓
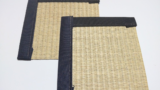
小満の頃に旬を迎える食べ物「とうもろこし」
とうもろこしというと真夏に食べるイメージがありますが、暦の上では既に夏とはいえ、とうもろこしは、6月が一番美味しい時期となります。
とうもろこしは、収穫すると糖分が時間とともに落ちていくので、収穫したらすぐに食べたい食品です。ただ、農家さんでなければ、収穫してすぐには食べることはできません。
ただ農家さんもこの最高に美味しいとうもろこしを食べていただきたいと、とうもろこしの産地でもある地元三島では、早朝に収穫したとうもろこしを朝9時から販売してくれるというイベントを6月の毎週土日に行ってくれます。これには、収穫仕立てが一番美味しいことをご存じの地元の方で長蛇の列ができます。でも、美味しいとうもろこしを食べることができるならば、長蛇の列など問題ありません。
この美味しさを知ってしまったら、他のとうもろこしが食べられなくなります。
それだけ、採れ立てのとうもろこしは美味しいということです。ご承知おきください。
「とうもろこし」についてはこちら ↓↓↓

小満の頃に食べる和菓子「水羊羹」
暑くなってくると食べたくなるのが、冷たい和菓子です。
冷たい和菓子は数あれど、やはりあんこ好きには定番の水羊羹が食べたくなります。カップなどに入った水羊羹が多いですが、切り分けて好きなだけ食べることができる水羊羹が、なんとも美味しくて好きです。
切り分けて食べる水羊羹といえば、福井の冬限定(11月~3月)の水羊羹が有名です。冬にこたつで水羊羹を食べるというものです。こたつで食べていたら、全部食べてしまいそうで怖いです。
「久保田の水羊かん」を、冬限定のお届けとなりますが、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

「羊羹・水羊羹」についての記事はこちら ↓↓↓

小満の頃に咲くお花「紫陽花」

紫陽花の花も園芸品種が増え、本当にいろいろな種類の紫陽花があります。
でも雨の日にこれだけ綺麗に咲くお花は、紫陽花だけです。晴れている日よりも、雨の日の方がイキイキしている花は、紫陽花だけです。水が好きならば、蓮や睡蓮のように水辺に咲けばいいのに、紫陽花は陸に咲くお花です。花や葉に水を浴びるが好きなのでしょう。
紫陽花が咲いている間は、たくさん雨が降りますように。
「紫陽花」についてはこちら ↓↓↓

明日はどんな手仕事する?
子供の頃、近くに桑の木があり、近所のお姉ちゃんがよく蚕を飼っていました。私は、気持ちが悪くて、手も出せませんでしたが、そのお姉ちゃんは、桑もとってきて、育てていました。
その後どうしていたかまでは覚えていませんが、桑の木があった場所だけは覚えています。もうマンションとかになってしまってますけど。でもそんな思い出も今になっては、大切な経験のひとつとしていられることに感謝です。
それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
次の二十四節気「芒種(ぼうしゅ)」
次の二十四節気は「芒種(ぼうしゅ)」です。↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「暦と食としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓









コメント