七草というと「春の七草」が有名です。
お花の中では「秋の七草」も知られてはいますが、実は「夏の七草」や「冬の七草」もあるのをご存じでしょうか。
すべてを同じ人が同じ時に決めたわけではない七草のくくりではありますが、それぞれの季節を楽しんでいただけると嬉しいです。
もっと知りたい「春の七草」
「春の七草」は、4つの七草の中では一番よく知られている1月7日に食べる「七草粥」に入れる七つの草花になります。
平安時代の頃は「七草粥」ではなく、「七種粥」として、米、粟、黍(きび)、稗(ひえ)、篁子(みの)、胡麻、小豆の7種類の穀物を炊いたお粥がありました。これに由来し、江戸時代に、徳川家の畑に生えていた七つの草が今の「七草粥」になったとされています。
「七草粥」について詳しくはこちら ↓↓↓

春の七草①せり 芹
「せり」についてはこちら ↓↓↓

春の七草②なずな 薺
◆別名
「ペンペン草」
風に揺れた時の音がペンペンと音がすることから。
「三味線草(シャミセングサ)」
種実の形が三味線のバチに似ているから。
◆原産地
西アジア。
◆科属
アブラナ科ナズナ属の2年草。
◆お花の名前の由来
諸説あり。
①切り刻むという意味の「なず」に菜がついた説。
②秋に芽生え、春に花が終わると夏になくなるから「夏無」で「なずな」という説。
③撫でたいほど可愛いという「愛でる花」を意味する「撫菜」から「なずな」になったという説。
◆歴史
麦が伝えられた時に、その種子と共に渡来した帰化植物です。
◆なずなの芽

◆開花時期
2月中旬~5月中旬。
◆花(植物)の特徴

繁殖力が旺盛なため、邪気を払い万病を避けられると言われています。
◆実の特徴
花が終わると実ができ、実はハート形をしており、真ん中で裂け、実(種)が出てきます。
◆食用としてのおすすめメニュー
お浸し、和え物、汁もの、天ぷらなど。種子はマスタードの代用になります。
◆効能
煎薬として、利尿、解熱、止血、洗顔料に用いられます。消化をよくするとされるジアスターゼを含みます。
◆花言葉
「全てを君に捧げる」

春の七草③ごぎょう 御形

◆別名
別名「母子草(ははこぐさ)」ともいい、子が母にまつわりつく様子にたとえました。
◆科属
キク科ハハコグサ属。
◆歴史
昔は、草餅には「ごぎょう(母子草)」が使われていました。今では草餅は「よもぎ」を使います。
◆何年草
1年草。
◆花の咲き方
お花が咲いた姿は、仏様のようだと表現します。
◆効能
乾燥したものは、せきやタンに効き、のどの痛みを和らげる効果があります。
春の七草➃はこべら 繁縷

◆別名
別名「はこべ」「ひよこぐさ」「すずめぐさ」「こはこべ」「あさしらげ」などとも言います。
◆科属
ナデシコ科。
◆お花の名前の由来
茎が長く、葉が対になってへらのようなので、この名があります。摘んでも摘んでもどんどん生えてくるので、繁栄が蔓延る(はびこる)と言われています。
◆何年草
2年草。
◆花の色
白い花が印象的。
◆効能
天日乾燥したものは、産後浄血、催乳に効果があります。歯茎を保つのにも役に立ちます。
◆食べ方
茎がシャキシャキしていて、水菜のようなので、生でサラダなどで食べられます。和え物やみそ汁の具などにもなります。
春の七草⑤ほとけのざ 仏の座

◆和名
正式名「小鬼田平子(コオニタビラコ)」。「田平子(たびらこ)」とも呼びます。
◆科属
キク科。
◆お花の名前の由来
5ミリくらいの黄色の花が円座のように咲くので、「仏の座(ほとけのざ)」といいます。
◆何年草
2年草。
◆開花時期
3月頃から。
◆効能
熱を下げたり、痛みを抑えたりします。
◆エピソード
5月頃になると、草丈「50センチにもなる「鬼田平子(おにたびらこ)」という、「小鬼田平子(こおにたびらこ)」よりも大きなサイズの別のお花が咲きます。「小(こ)」がなくなり、大きくなったお花です。
春の七草⑥すずな 菘・鈴菜
かぶの別名。葉にはカロチンやビタミンを多く含み、消化促進の効果もあります。胸やけや胃の痛みなどを抑えます。神を呼ぶ鈴とされています。
「かぶ」についてはこちら ↓↓↓

春の七草⑦すずしろ 蘿蔔・清白
大根の別名。葉には、ビタミンや鉄分などが豊富に含まれます。根の汁は、打撲や火傷に効きます。汚れのない純白を意味します。
「大根」についてはこちら ↓↓↓



もっと知りたい「夏の七草」
「夏の七草」は、暑い夏でも涼しさを感じさせてくれる観賞用の植物七種類です。
夏の七草①よし 葦
「よし」についてはこちら ↓↓↓

夏の七草②いぐさ 藺草
「いぐさ」についてはこちら ↓↓↓
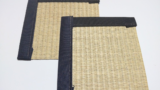
夏の七草③おもだか 沢瀉 面高
◆別名
「花慈姑(はなぐわい)」「三角草(さんかくぐさ)」「芋草(いもぐさ)」「おとげなし」などと呼ばれます。
◆分布
日本全土、東南アジアなど。
◆科属
オモダカ科オモダカ属の多年草。
◆分類
水生植物。
◆自生場所
水田や用水路、浅い池などに自生。
◆葉
矢じり型。矢が下を向く。ハートの逆型。長さ7~15センチ。
◆草丈
50センチほど。
◆花径
1.5~2センチ。
◆花びら
一重咲き。3枚。
◆花の色
白。
◆花の特徴
花が3個づつ咲きます。
夏の七草➃ひつじぐさ 未草(すいれん 睡蓮)
「未草・睡蓮」についてはこちら ↓↓↓

夏の七草⑤はちす・はす 蓮
「蓮」についてはこちら ↓↓↓

夏の七草⑥こうほね 河骨
「河骨」についてはこちら ↓↓↓

夏の七草⑦さぎそう 鷺草
◆別名
「サギラン」
◆科属
ラン科サギソウ属の多年草。
◆分布
関東以西の本州、四国、九州に自生。
◆お花の名前の由来
白鷺が翼を広げて飛び立った姿に似ていることからこの名が付いたとされます。
◆自生場所
日当たりの良い湿地。
◆草丈
15~50センチ。
◆花びら
唇弁が著しく大きく、白鷺(しらさぎ)が翼を広げて飛び立ったように扇状に広げて開く。左右の裂片の縁は、糸状に切れ込み、より一層飛んでいる白鷺に似ています。
◆開花時期
7月~9月。
◆花径
横幅約3センチ。
◆花の色
白。
◆ 花言葉
「無垢」
「清純」
「繊細」
「神秘的な愛」
「夢であなたを想う」
「芯の強さ」
もっと知りたい「秋の七草」
「秋の七草」は、観賞用のお花です。
『万葉集』(7~8世紀後半に編纂。奈良時代末期)に、山上憶良が「秋の七草」の句を歌っています。これが「秋の七草」のいわれとされています。
「秋の七草」の覚え方としては、それぞれのお花の頭文字を上記順番で並べると「ふくはおすきな」になります。「福はお好きな」「服はお好きな」という形で覚えていただけると簡単です。
秋の七草①ふじばかま 藤袴
「藤袴」についてはこちら ↓↓↓

秋の七草②くず 葛
「葛」のお花についてはこちら ↓↓↓

秋の七草③はぎ 萩
「萩」のお花についてはこちら ↓↓↓

秋の七草➃おみなえし 女郎花
「女郎花」についてはこちら ↓↓↓

秋の七草⑤すすき 芒、薄
「すすき」についてはこちら ↓↓↓

秋の七草⑥ききょう 桔梗
「桔梗」についてはこちら ↓↓↓

秋の七草⑦なでしこ 撫子
「撫子」についてはこちら ↓↓↓

もうひとつの「秋の七草」 あさがお 朝顔
別の説として、桔梗が朝顔だったという説があります。
現在の朝顔は、奈良時代末期に中国より渡来したもので、それ以前は、桔梗のことを「朝顔」と呼んでいたとされます。もともとは「朝顔」と呼ばれていた「桔梗」のお花が秋の七草だったということなのですが、今では、呼び名が「朝顔」でも「桔梗」でも、間違いではないとされています。
「朝顔」についてはこちら ↓↓↓

もっと知りたい「冬の七草」
「冬の七草」は、「冬至の七種」のことを「冬の七草」とも言いますので、「冬至の七種」の冬の七草のことを「食の冬の七草」といい、下記は「花の冬の七草」になります。
「食の冬の七草」については、こちら ↓↓↓

この草花の「冬の七草」は、明治37年(1904年)の「時事新報」に掲載されたとされます。
冬の七草①ふきのとう 蕗の薹
「蕗の薹」についてはこちら ↓↓↓

冬の七草②ふくじゅそう 福寿草
「福寿草」についてはこちら ↓↓↓

冬の七草③せつぶんそう 節分草
◆英名
eranthis pinnatifida
◆科属
キンポウゲ科セツブンソウ属。
◆開花時期
2月の節分の頃。
◆花びら
一重咲き。5枚。
◆花の色
白、黄緑、ピンクなど。
◆花径
2センチ程。
◆花の咲き方
唐子(からこ)咲きもあります。 唐子咲きとは、花の咲く様子が、唐子人形の髪を結った形に似ていることから呼ばれています。
◆花の特徴
長いガクのようなものが6枚あり、花びらのようにも見える不思議なお花です。
◆エピソード
「節分草」とはいえ、咲くのは、2月の節分の時だけです。5月、8月、11月の節分には咲きません。
冬の七草➃ゆきわりそう 雪割草
◆分布
北陸や東北地方などの寒い地域。
◆科属
キンポウゲ科ミスミソウ属。
◆葉
3枚。
◆開花時期
3月頃。
◆花の色
ピンク、白、紫色。
◆花の咲き方
花の咲き方により、種類が無限にあります。
・標準花
花びらが一重で6枚。色はピンク。
・二段咲き
おしべが花のようになって、花びらと共に二段に咲いているように見えます。
・三段咲き
おしべ、めしべ、花びらが三段で咲いているように見えます。
・千重(せんえ)咲き
花びらが、八重咲きの更に上をいく重なり方をしています。
・テンテン花
花びらの模様がランダムになっています。
・覆輪
花びらの外側が違う色になっており、絞り模様のようになっています。
◆花の特徴
「山野草園芸」といい、人の手ではなく、野の中で自然に変化して出来上がる花を「花芸」といい、葉を「葉芸」と言います。雪割草は、この「山野草園芸」が特徴です。
冬の七草⑤かんあおい 寒葵
◆科属
寒葵は、葵という名前が付いていますが、アオイ科のお花ではなく、ウマノスズクサ科カンアオイ属のお花です。
◆お花の名前の由来
葉の形がアオイの葉に似ていることから、この名が付けられました。
◆自生場所
林の中に自生。
◆葉
シクラメンのような形をしています。葉は常緑。
◆開花時期
9月頃から咲き始め、3月くらいまで咲き続けます。
◆花の咲き方
枯れ葉に埋もれているように花が咲きます。
◆花の特徴
野で見つける際には、ハート型をしており、深い緑色の葉を探しましょう。
冬の七草⑥かんぎく 寒菊

◆英名
winter chrysanthemum
◆交配
アブラギクという原種の園芸品種。
◆開花時期
寒菊は、12月から1月の寒の頃に咲く菊のことを言います。
「菊」についてはこちら ↓↓↓

冬の七草⑦すいせん 水仙
「水仙」についてはこちら ↓↓↓

明日はどんな手仕事する?
「七草」といっても、草だけでなく、食べるものから、観賞用のお花までいろいろあり、このようにまとめてみると楽しいですね。
今回まとめた、それぞれの七草は、あくまでもそれぞれの季節で言われていることで、言われている時代背景などもすべて違い、共通したものではありません。予めご了承ください。
古くから言い伝えられたいることは、七つをひとくくりにまとめるのが好きだったのでしょう。
それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓










コメント