「河骨(こうほね)」というお花をご存じでしょうか。
お花屋さんなどでは、もちろん見かけないお花です。
いけばなをされる方でも、特別な時でないと、普段のお稽古などではいけることができないお花です。
蓮などに育つ環境が似てはいますが、家で育てている方も滅多にいないお花です。
そんな「こうほね」の魅力や「こうほね」をいける際の下準備の方法に迫ります。
もっと知りたい「河骨(こうほね)」の魅力
こうほねの漢字
「河骨」または「川骨」と書きます。
こうほねの科属
スイレン科。
こうほねの分類
多年生水草。
こうほねの自生場所
川、沼、池などの水辺。
こうほねの生態系
蓮や睡蓮よりも深いところに生育し、水深2mほどの川岸や池沼にも群落を作ります。
こうほねの歴史
元禄8年(1695)刊『花壇地錦抄』には、「茎1本に金色の花が1輪咲く花が運命的なもの(のように綺麗)」と、また、宝永5年(1708)刊『大和本草 八之下』にも、「茎一花を開く賞に堪たり(価値があるほどに美しい)」と描かれています。泥中に生育しながらもここまで綺麗に咲く「こうほね」のお花は、昔から称賛されていたのでしょう。
こうほねのお花の名前の由来
根茎が白く太く、動物の骨のようなのでこの名が付いたとされます。
こうほねの根(地下茎)
わさび状の根茎が白く太い。地中浅くに横臥し、分岐して良く増えます。
こうほねの葉
泥中に生育しているにもかかわらず、葉は濃緑で、光沢があり、とても綺麗です。
こうほねの開花期間
残念ながら、「こうほね」は、切り花にすると1日花です。大切にいけて、たっぷり楽しみましょう。
こうほねの花の色
花の色は、凛々しい黄色です。金色とも表現されます。
こうほねの季語
季語は「夏」です。
こうほねのエピソード
「こうほね」は、夏の七草のひとつです。
夏の七草を含む「四季の七草」についてはこちら ↓↓↓

こうほねのいけ方のコツ
こうほねをいける際に準備すること
「こうほね」は、水が下がりやすいので、水揚げポンプで水揚げをしてから始めましょう。葉だけでなく、花にも全て、水揚げをします。
こうほねの水揚げポンプを使った水揚げ
水揚げポンプを使っての水揚げの準備として、バケツ3個、水揚げポンプ、乾燥を防ぐために葉に塗る馬油、延命剤または灰汁、雑巾などを用意しましょう。
バケツは、①今、こうほねを入れてあるバケツ、②延命剤や灰汁などを入れた綺麗なお水を入れるバケツ、③下処理をしたものを入れるバケツの3個が必要です。
延命剤や灰汁を混ぜると持ちがよくなります。灰汁は、灰が沈んだあとの水をポンプで入れ込みます。
水揚げポンプで注入すると、水が入っていくのが目でみてわかります。必ず、葉の先まで水が入ったことを確認しましょう。
また、急激にポンプで水を注入すると、茎が破れることもあります。優しく水揚げをしてあげてください。
水揚げポンプをお持ちでない方は、こちらからお取り寄せができます。霧吹きとしても使えるタイプです。↓↓↓

乾燥を防ぐために塗る馬油
葉の表面が乾燥しやすいのと、水が下がらないよう、葉に馬油を塗ってあげると良いでしょう。
塗る馬油がなければ、ハンドクリームの「ももの花」でも代用可能です。「ももの花」は、ドラッグストアなどで販売してます。チューブのタイプもありますが、たっぷり入ったこちらのサイズがおすすめです。こちらからも購入可能です。↓↓↓

こうほねのいけ方の注意
「こうほね」は、下準備さえしっかりできれば、とても撓めやすく、いけやすいお花です。不思議な花と綺麗な葉を上手に生かしていけてみてください。
「かう骨」という名を忌んで、祝儀の場には用いないようにします。
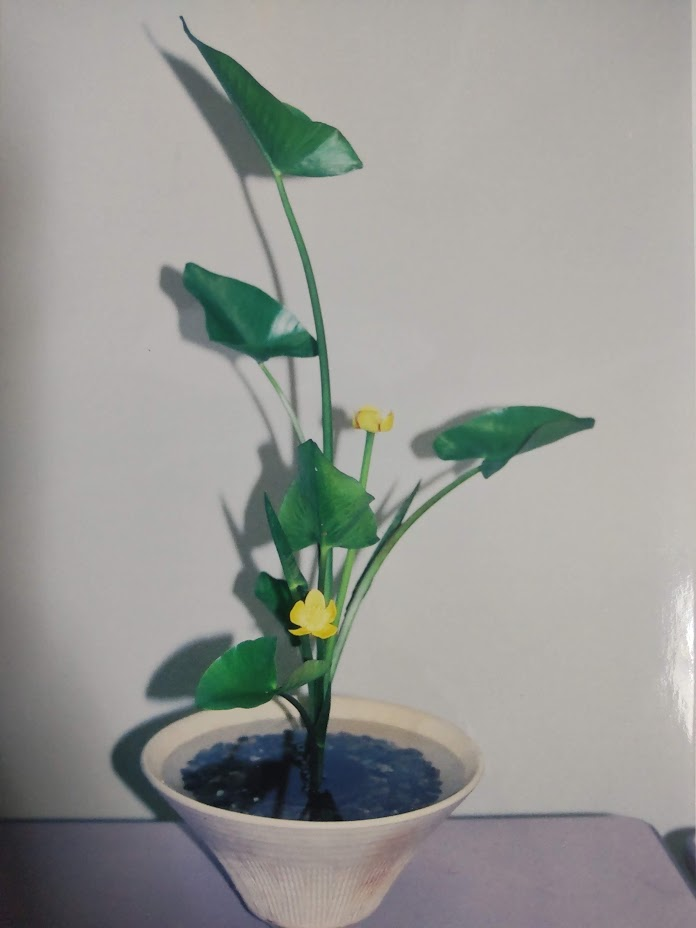
こうほねのおすすめの花器
花器は、水物のお花なので、広口の花器が良いでしょう。
こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

お花の関連記事
◆「お花の名前別まとめ(写真付き)」の記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」についてのまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓









コメント