「伝統野菜」とは、「食べる文化遺産」として、古くから栽培されてきた野菜です。
日本全国にある知己特有の「伝統野菜」や地域の「ブランド野菜」と呼ばれるものをまとめてみました。
人気があり全国に知れ渡っている野菜もあれば、絶えてしまいそうな野菜もあります。それぞれの地域で、たくさんの人によって、守られている野菜たちです。
都道府県を北から順に並べてあります。
北海道
北海道の伝統野菜
きゃべつ「札幌大球」
約20kgもある大きなきゃべつ。
青森県
「青森県伝統野菜」
とうがらし「清水森ナンバ」
「清水森ナンバ」についてはこちら ↓↓↓

にんにく「たっこにんにく」
青森県田子町で作られるにんにくのこと。
なっぱ「下北春まな(青森県)」
「下北春まな(青森県)」についてはこちら ↓↓↓

秋田県
秋田県の伝統野菜
だいこん「松館しぼり大根」
「松館しぼり大根」についてはこちら ↓↓↓

山形県
「山形県の伝統野菜」についてはこちら ↓↓↓

福島県
福島県の伝統野菜
かぼちゃ「奥会津金山赤かぼちゃ」
空中で吊って育てるかぼちゃ。
せり「相馬せり」
◆産地 福島県相馬市
◆分類 湧き水で水中栽培する「田せり」
◆出荷開始時期 10月下旬~
◆旬 10月下旬~1月
◆草丈 約40センチ
◆特徴
相馬せりは、アクがないので、お子様でも食べることができます。根が長いと出来が良いとされます。
東京都
「江戸東京野菜」
東京都の伝統野菜「江戸東京野菜」は、現在52品種が登録されています。
オクラ「八丈オクラ」
かぶ「金町こかぶ」
かぶ「品川かぶ」
江戸時代の品川宿の繁栄と共に発展した「品川かぶ」。小ぶりなのに、甘みがあり、煮崩れしにくいかぶです。
かぼちゃ「内藤かぼちゃ」
きゅうり「馬込半白きゅうり」
ごぼう「滝野川ごぼう」
しょうが「谷中しょうが」
だいこん「大蔵大根」
「大蔵大根」についてはこちら ↓↓↓

だいこん「亀戸大根」
「亀戸大根」についてはこちら ↓↓↓

だいこん「高井戸大根」
だいこん「練馬大根」
「練馬大根」についてはこちら ↓↓↓

とうがらし「内藤とうがらし」
新宿のビルの屋上で栽培されている唐辛子です。
なす「雑司ヶ谷なす」
なす「寺島ナス」
江戸川区で栽培されています。サイズは小さく、卵くらいの大きさ。皮がかたく、実がしっかりしている。生よりも火を通した方が美味しい。
にんじん「砂村三寸人参」
にんじん「滝野川人参」
にんじん「馬込三寸人参」
ねぎ「千住ねぎ」
みょうが「早稲田みょうが」
神奈川県
神奈川県の伝統野菜
だいこん「三浦大根」
「三浦大根」についてはこちら ↓↓↓

ブランド野菜「鎌倉野菜」
「鎌倉野菜」とは、神奈川県鎌倉市周辺で栽培されている野菜のことで、ブランド野菜となります。紫のカリフラワーや黄色のズッキーニなど、伝統品種ではなく、色鮮やかであったりおしゃれな野菜が多数あります。
山梨県
山梨県の伝統野菜
じゃがいも「こうしゅういも 甲州いも」
じゃがいもは、江戸時代初期に、ヨーロッパからオランダ商人の手でジャカルタを経由して長崎の出島に入りました。出島から中井清太夫(1732~1795)という甲斐国(現在の山梨県)の代官を務めた幕府の役人が、飢饉になった時に長崎で見たじゃがいもを思い出して、甲斐で作ったらそれが大成功したと言われています。そのことをきっかけに、江戸時代から明治時代にじゃがいものことを「甲州いも」と呼ぶようになりました。隣国信濃国(現在の長野県)の「下栗いも」や祖谷渓(現在の徳島県三好市)の「ごうしゅういも」などに広まり、近年の信州大学の調査の結果、「甲州いも」は「下栗いも」と同じDNAグループに属することがわかったそうです。
なっぱ「鳴沢菜」

長野県
「信州の伝統野菜」
「信州の伝統野菜」は、種類が83種類あると言われています。
きゅうり「開田きゅうり」
きゅうり「佐久古太きゅうり」
きゅうり「清内路きゅうり」
きゅうり「番所きゅうり」
きゅうり「松代青大きうり」
きゅうり「八町きゅうり」
山菜「おこぎ」
長野県飯田市で採れる山菜。「おこぎ」とは南信州の方言で、正確には「うこぎ」のこと。木から出る新芽を食べます。樹高は2メートルほど。4月中旬が旬。シャキシャキとした食感で、お浸しや天ぷら、かき揚げなどにします。
じゃがいも「下栗いも(しもぐりいも)」
長野県飯田市の標高1100mの急斜面で作られているじゃがいも。現在生産者は、20軒ほどしかいない。ピンポン玉くらいの小振りのじゃがいも。昼夜の寒暖差が甘みをもたらします。南向きの斜面を使い、日当たりが抜群に良いところで育てています。地元の方は、味噌、えごま、砂糖を混ぜた「えごま味噌」をかけた「田楽いも」にして食べています。近辺の直売所では、9月から11月に販売されます。
とうがらし「牡丹胡椒」
「信州の伝統野菜」の1つ。
「牡丹胡椒」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「野沢菜」
「野沢菜」についてはこちら ↓↓↓

ねぎ「松本一本葱」
信州の伝統野菜の1つ。江戸時代から作られている太いねぎで、90度くらいに曲がっています。夏の暑い時期に植え替えをし、横に植えて土をかぶせることで、冬までに上に伸びるので曲がっているねぎになります。曲がった日に当たらない白い部分に糖分が集まり、甘いねぎになります。鉄火みそやねぎみそ、根っこの天ぷらなどにして食べます。
新潟県
「長岡野菜」
新潟県長岡市(南魚沼地域)の伝統野菜をいいます。
とうがらし「かぐら南蛮」
かぐら南蛮は、「長岡野菜」に指定されています。
「かぐら南蛮」についてはこちら ↓↓↓

静岡県
静岡県の伝統野菜
なっぱ「水かけ菜」
御殿場市や小山町でしか採れない「水かけ菜」についてはこちら ↓↓↓

ブランド野菜「箱根西麓三島野菜」
静岡県三島市の箱根山西側斜面で採れるブランド野菜「箱根西麓三島野菜」についてはこちら ↓↓↓

愛知県
「あいちの伝統野菜」
だいこん「守口大根」
守口大根は、現在の大阪府守口市が原産と言われています。
現在では主に、岐阜県各務原市や愛知県丹羽郡扶桑町などで作られています。
「守口大根」についてはこちら ↓↓↓

にんじん「碧南鮮紅五寸人参」
「碧南鮮紅五寸人参」は、「にんじん③人参の品種」をご覧ください。↓↓↓

三重県
三重伝統野菜
だいこん 御薗大根
「御薗大根」についてはこちら ↓↓↓

岐阜県
岐阜県は、北部の飛騨地方と南部の美濃地方に分けられています。
「飛騨伝統野菜」
飛騨地方は県北部にあり標高が高く冷涼な気候からできる野菜が多くなります。
飛騨地方には、高山市や飛騨市、下呂市などが属します。
かき「南飛騨富士柿」
飛騨伝統野菜。
かぶ「種蔵紅かぶ」
飛騨伝統野菜。
かぶ「飛騨紅かぶ」
飛騨伝統野菜。
さんしょう「高原山椒」
飛騨伝統野菜。
ねぎ「飛騨一本太ねぎ」
飛騨伝統野菜。
「美濃伝統野菜」
美濃地方は県南部にあり、平野が広がる温暖な気候からできる野菜になります。
美濃地方には、岐阜市、大垣市、各務原市などが属します。
かき「堂上蜂屋柿」
美濃伝統野菜。
ごぼう「菊ごぼう」
美濃伝統野菜。
だいこん「守口大根」
美濃伝統野菜の1つ。
守口大根は、現在の大阪府守口市が原産と言われています。
現在では主に、岐阜県各務原市や愛知県丹羽郡扶桑町などで作られています。
「守口大根」についてはこちら ↓↓↓

ねぎ「徳田ねぎ」
美濃伝統野菜。
まめ「桑の木豆」
美濃伝統野菜。
どちらにも属す岐阜県の伝統野菜
岐阜県内で栽培されていることに間違いはありませんが、確実な線引きが難しいのが「飛騨伝統野菜」と「美濃伝統野菜」です。
とうがらし「あじめこしょう」
飛騨伝統野菜にも、美濃伝統野菜にも認定されています。
「あじめこしょう」についてはこちら ↓↓↓

石川県
「加賀野菜」
石川県金沢市の「加賀野菜」についてはこちら ↓↓↓

滋賀県
滋賀県の伝統野菜
とうがらし 「弥平唐辛子」
滋賀県の伝統野菜の1つ。
「弥平唐辛子」についてはこちら ↓↓↓

奈良県
「大和伝統野菜」
奈良県で古くから栽培されている「大和伝統野菜」に認定されている野菜です。
だいこん「女山大根」
奈良県の「大和伝統野菜」のひとつ。
奈良県の「女山大根」についてはこちら ↓↓↓

とうがらし「ひもとうがらし」
奈良県の「大和伝統野菜」のひとつ。
「ひもとうがらし」についてはこちら ↓↓↓

とうがらし「紫とうがらし」
奈良県の「大和伝統野菜」のひとつ。
「紫とうがらし」についてはこちら ↓↓↓

とうがらし「大和甘長とうがらし(大和の甘とう)」
奈良県の「大和伝統野菜」のひとつ。
「大和甘長とうがらし(大和の甘とう)」についてはこちら ↓↓↓

とうがらし「大和とうがらし」
奈良県の「大和伝統野菜」のひとつ。
「大和とうがらし」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「下北春まな(奈良県)」
「大和伝統野菜」の1つ。
「下北春まな(奈良県)」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「大和まな」
「大和伝統野菜」の1つ。
「大和まな」についてはこちら ↓↓↓

京都府
「京野菜」
京都府には「京の伝統野菜」や「ブランド京野菜」のくくりがあり、それぞれに含まれる含まれないがあり、野菜の種類も多いため、「京野菜」としてまとめてあります。詳しくはこちら ↓↓↓


大阪府
「なにわ伝統野菜」
きゅうり「南河内毛馬胡瓜」
長さ約30cm。白と緑のツートンカラーの胡瓜。
だいこん「守口大根」
守口大根は、現在の大阪府守口市が原産と言われています。
現在では主に、岐阜県各務原市や愛知県丹羽郡扶桑町などで作られています。
「守口大根」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「大阪しろ菜」
「大阪しろ菜」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「黒菜」
「黒菜」についてはこちら ↓↓↓

くわい「大阪のくわい」
「なにわ伝統野菜」の1つ。
歴史のある小粒の慈姑。大阪・吹田地区で栽培されています。生産量が少なく、現在はあまり出回っていません。 別名「ひめくわい」とも呼ばれています。
兵庫県
兵庫県の伝統野菜
なっぱ「播州コブ高菜」
葉の根元にコブがある高菜。
なっぱ「ちぢみほうれんそう」
「ちぢみほうれんそう」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「ばんせいな」
「ばんせいな」についてはこちら ↓↓↓

広島県
広島県の伝統野菜
だいこん「高野大根」
「高野大根」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「広島菜」
「広島菜」についてはこちら↓↓↓

岡山県
岡山県の伝統野菜
黒大豆「作州黒(さくしゅうぐろ)
岡山県勝英地域(美作市など)で作られている大粒の黒大豆。11月が旬。
鳥取県
鳥取県の伝統野菜
とうがらし「三宝甘長とうがらし」
甘唐辛子。
徳島県
徳島県の伝統野菜
じゃがいも「ごうしゅういも」
徳島県三好市の祖谷渓で古くから栽培されてきたじゃがいもの在来の品種です。地元では「ごうしも」「おくいも」「ほどいも」などとも呼ばれています。標高の高い急傾斜地で育てられ、小振りで煮崩れしにくく、味が濃いのが特徴です。皮の色によって「赤いも」と「白いも」に分かれ、それぞれを「平家」「源氏」に見立てて「源平いも」というブランド名で販売しています。
高知県
高知県の伝統野菜
とうがらし 土佐甘とう
「土佐甘とう」についてはこちら ↓↓↓

福岡県
福岡県の伝統野菜
なっぱ「大葉春菊」
「大葉春菊」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「かつお菜」
「かつお菜」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「やましお菜」
福岡県久留米市北野町でしか作られていない。江戸時代に筑後川が何度も水害を起こし、種が流れてきて北野町の土と合い、作られるようになったと言われています。山崩れのことを久留米の方言で「やましお」ということから、この名が付いたと言われています。からし菜の一種。からしの風味がします。栽培時期は、10月~3月。塩で一夜漬けしたお漬物「やましお漬け」が有名。他にも、巻きおにぎりにしたり、味噌汁に入れたり、サンドイッチにして食べたりします。
長崎県
長崎県の伝統野菜
じゃがいも「デジマ」
ホクホク系とねっとり系の中間のじゃがいもの品種。昔ながらの品種。じゃがいもが長崎県の出島から広がったことからこの名が付いたとされます。栽培が難しいため、あまり世には出ていません。ホクホクして皮が薄いのが特徴。焼きじゃがいもが美味しい。
佐賀県
「唐津野菜」
じねんじょ「唐津自然薯」
佐賀県唐津市産。畑で育てている自然薯。1kg3万円を超える高級品。波板を使って斜めに栽培。長く、太く、真っ直ぐな自然薯。
だいこん「おんなやまだいこん 女山大根」
佐賀県の「女山大根」についてはこちら ↓↓↓

佐賀県産の野菜がセットになったものを、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

熊本県
「肥後伝統野菜」
なす「大長なす」
熊本県植木町産。
にんじん「熊本長にんじん」
「肥後伝統野菜」の1つ。
「熊本長にんじん」についてはこちら ↓↓↓

鹿児島県
鹿児島県の伝統野菜
だいこん「桜島大根」
「桜島大根」についてはこちら ↓↓↓

沖縄県
「島野菜」
とうがらし「島とうがらし」
「島とうがらし」についてはこちら ↓↓↓

なっぱ「はんだま」
熱帯アジア(東南アジア)原産で、中国や台湾を経由して沖縄に伝わった野菜。和名を「水前寺菜(すいぜんじな)」と呼ぶ。キク科の多年草。シャキシャキとした葉物。葉の表が緑色で、裏が紫色をしています。ポリフェノールが豊富で、貧血改善に効果があります。
「琉球料理」では、「スーネー(白和え)」にするのが一般的です。
明日はどんな手仕事する?
「伝統野菜」の種類は、無限にあります。私の住んでいる地域だけでもたくさんあるのに、全国に手を広げてしまうのは、いかがかと思いました。
ただ、時間は待ってくれません。絶えてしまう野菜もあることは事実です。美味しくて人気になる種類は良いのですが、それに押されて絶えてしまう種類もあるということです。できれば、そのようにならないためにも、日々調査できればと思っております。
少しずつにはなりますが、こちらのまとめ記事を更新し、詳しくは現地の情報を見ていただくのも良いのかもしれません。少しでもお役に立てるよう、更新を続けます。
それでは、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
日本全国の伝統野菜の関連記事
◆伝統野菜を使って作る「郷土料理・伝統料理」の記事はこちら ↓↓↓

◆伝統野菜を使って作る「お雑煮」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓








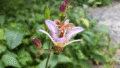
コメント