お花の歴史を語る上で忘れてはいけないのが日本原産のお花です。ただし、日本原産のお花が少ないことは、本当にびっくりします。ほとんどが、海外から伝来したお花になります。そこで、日本原産のお花や植物の紹介です。
日本原産とは
「日本原産」というと日本で生まれ、日本で育ったという解釈になりがちですが、植物学上ではより細かい解釈があります。
遺存種(いそんしゅ)
2000万年以上前、日本列島はアジア大陸の一部でした。1500万年前頃に、アジア大陸から離れ、現在のような島国の日本ができたと言われています。
「遺存種」とは、この日本がアジア大陸と陸続きだった頃からある植物で、陸が離れてもそれぞれもしくはどこか一部で生存し続けた植物になります。
具体的には、カツラ、トチノキ、クリなどが「遺存種」と言われています。
固有種(こゆうしゅ)
日本にしか存在しない植物。
例えば、屋久杉は屋久島にしかない「固有種」。他にも、ニホンカエデ、アマギツツジなどが「固有種」です。
在来種(ざいらいしゅ)
外国から人が持ち込んだものではない、もともと日本に自然分布していた植物となります。
日本原産と言われている植物
上記の通り、「日本原産」という表現はかなり曖昧な表現にはなります。例えば、百合は、外国にも古くからたくさんの種類がありますので、百合の原産は日本ではないのですが、日本原産の百合の種類があるという意味で、ここに載せたりもしています。難しい分類の仕方ではありますが、「外来種」ではない植物という意味で捉えていただいても良いのかと思われます。あいうえお順で並べてあります。
あやめ 文目 綾目 菖蒲
あやめは、日本にもともと自然分布していた在来種となります。
「あやめ」についてはこちら ↓↓↓

かきつばた 杜若 燕子花
1つの種類のお花を四季でいけ分けすることができる「かきつばた」についてはこちら ↓↓↓

かくれみの 隠蓑
日本の固有種。ウコギ科。「かくれみの」の名前の由来は、葉の形が昔の雨具であった「蓑(みの)」に似ていることからつきました。その葉は肉厚で、光沢があり、滑らかな皮のようです。夏に黄緑色の花が球状に集まって咲きます。実は、緑色から黒に変化します。
「かくれみの」は、「みつながしは(御網葉)」という名で『日本書紀』(720年編纂・歴史書)、『万葉集』(759年頃編纂・奈良時代末期・歌集)に描かれています。
かたくり 片栗
「かたくり」についてはこちら ↓↓↓
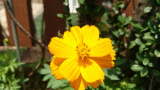
かつら 桂
「桂」は、日本と中国に自然分布する在来種であり遺存種でもあります。
「桂」についてはこちら ↓↓↓

かわらなでしこ 河原撫子
「なでしこ」の中でも、「河原撫子」は日本固有の変種です。
「なでしこ」についてはこちら ↓↓↓

ききょう 桔梗
桔梗は、東アジアに自生する植物で、日本の固有種でもあり在来種でもある植物です。
「桔梗」についてはこちら ↓↓↓

くり 栗
世界中には、栗の種類がたくさんあります。それぞれに特徴がある遺存種となります。
日本では、山に自生する自生種として「柴栗・芝栗(シバグリ)」「山栗(ヤマグリ)」があり、これを改良したものが「日本栗」、所謂「和栗」です。
「栗」の品種についてはこちら ↓↓↓

こうやまき 高野槇

高野槇は、日本にだけ自生している固有種です。常緑高木。コウヤマキ科。名前の由来は、和歌山県の高野山に多く自生していることから付けられました。別名「ホンマキ」。
さくら 桜
「桜」は、日本にもともと自然分布していた在来種となります。
「桜」についてはこちら ↓↓↓

ささ 笹
「笹」についてはこちらの「笹」をご覧ください。 ↓↓↓

しきみ 樒
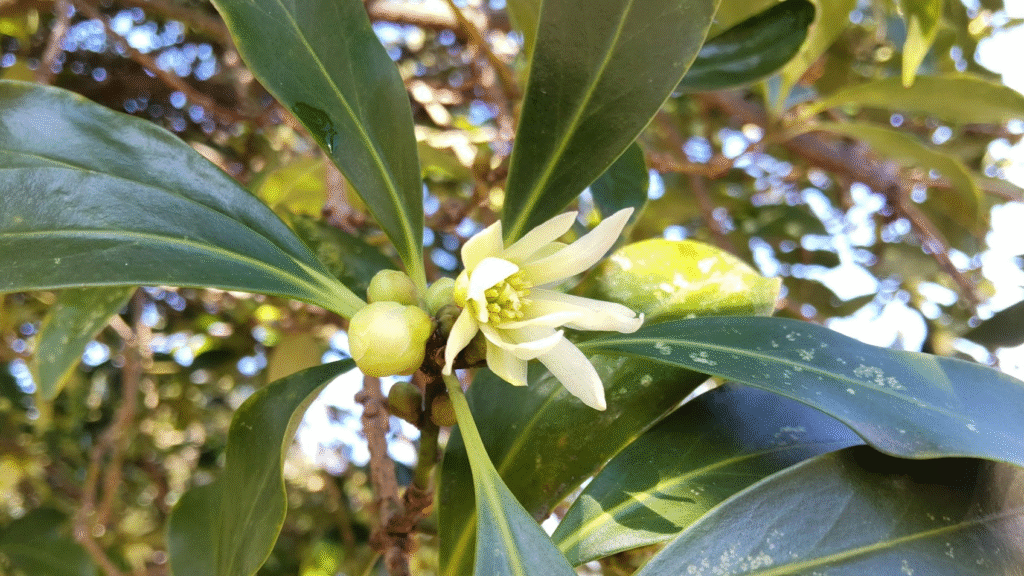
春に花を咲かせる「しきみ」。別名が非常に多く、たくさんの呼ばれ方をします。秋には八角のような星型の実がなります。常緑の葉が、仏事に使われます。『万葉集』(759年頃編纂・奈良時代末期・歌集)にも詠まれ、日本原産とされます。
すぎ 杉 椙
日本特産の常緑高木です。屋久島にある「屋久杉」が樹齢千年と言われ、他にも紀元前からあるとされる「紀元杉」や、推定樹齢7200年と言われる「縄文杉」など、桁違いに古い木があります。
すみれ
日本には50種以上の原種が自生しています。『万葉集』(759年頃編纂・奈良時代末期・歌集)にも詠まれている古くからあるお花。多年草ですが、数年で絶えてしまうの毎年種を取って育てるのがおすすめです。
たちばな 橘/はなたちばな 花橘
古くから日本に自生。日本のすべての柑橘の原種と言われています。
「橘/花橘」についてはこちら ↓↓↓

つつじ 躑躅
奈良時代末期の759年頃に編纂された『万葉集』にも載っています。
「つつじ」についてはこちら ↓↓↓
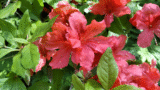
つばき 椿
「椿」は、日本と中国に自然分布する在来種。
「椿」についてはこちら ↓↓↓

トチノキ
遺存種。
ニホンカエデ
「ニホンカエデ」は、日本の固有種です。『万葉集』にも登場します。
「楓」についてはこちら ↓↓↓

ふじ 藤
藤は、ヤマフジやノダフジなど、日本原産の品種がいくつかあります。
「藤」についてはこちら ↓↓↓

フタバアオイ 二葉葵 双葉葵
奈良時代末期の759年頃に編纂された『万葉集』にも載っています。
「フタバアオイ」についてはこちら ↓↓↓

やまぶき 山吹
「山吹」についてはこちら ↓↓↓

ゆり 百合
百合は、日本原産の品種が多数あります。
「百合」についてはこちら ↓↓↓

ワダツミノキ
◆原産 鹿児島県奄美大島の固有種
◆科属 クロタキカズラ科
◆開花時期 5月下旬
日本原産のおすすめの逸品
古くからある日本原産のお花を育ててみませんか?桔梗の苗をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

お花の関連記事
◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓








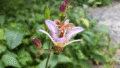

コメント