各地域で有名な和菓子から、その地域でしか食べられていない伝統のお菓子のご紹介です。
各地域で有名な和菓子の店舗名とその看板商品やおすすめの商品名のご紹介、またその地域で食べられている伝統的な郷土のお菓子なども加えて紹介しております。果てしない数のご案内になってしまいそうなので、ご紹介が多い都道府県は、リンクができるようにしてあります。
また、その商品もしくはそのお店の代表銘菓など、お取り寄せができるものは、載せさせていただいております。旅行に行った気分でお取り寄せもしてみてください。お取り寄せをしていないお店さんもございます。ご了承くださいませ。
和菓子の内容につきましては、「和菓子①和菓子の種類」をご覧ください。
都道府県名は北から、店舗名はあいうえお順となっております。
- 青森県の有名な和菓子
- 岩手県の有名な和菓子
- 宮城県の有名な和菓子
- 山形県の有名な和菓子
- 福島県の有名な和菓子
- 栃木県の有名な和菓子
- 茨城県の有名な和菓子
- 千葉県の有名な和菓子
- 埼玉県の有名な和菓子
- 東京都の有名な和菓子
- 神奈川県の有名な和菓子
- 新潟県の有名な和菓子
- 石川県の有名な和菓子
- 福井県の有名な和菓子
- 長野県の有名な和菓子
- 山梨県の有名な和菓子
- 静岡県の有名な和菓子
- 愛知県の有名な和菓子
- 三重県の有名な和菓子
- 岐阜県の有名な和菓子
- 滋賀県の有名な和菓子
- 京都府の有名な和菓子
- 大阪府の有名な和菓子
- 岡山県の有名な和菓子
- 広島県の有名な和菓子
- 島根県の有名な和菓子
- 香川県の有名な和菓子
- 徳島県の有名な和菓子
- 愛媛県の有名な和菓子
- 高知県の有名な和菓子
- 福岡県の有名な和菓子
- 佐賀県の有名な和菓子
- 長崎県の有名な和菓子
- 熊本県の有名な和菓子
- 宮崎県の有名な和菓子
- 鹿児島県の有名な和菓子
- 沖縄県の有名な和菓子
- 明日はどんな手仕事する?
- 和菓子の関連記事
- 季節の手仕事の関連記事
青森県の有名な和菓子
かねご製餡 匠あんこ堂「こびりっこ」
青森県八戸市。昭和43年(1968年)創業。あんを製造されている「かねご製餡」が菓子部門のブランドとして「匠あんこ堂」を新設されました。
「こびりっこ」とは、青森県の南部地方で食べられている郷土料理で、南部せんべいに甘めのお赤飯を挟んだものです。
「きんかもち」
「きんかもち」は、青森県南部地方で食べられている郷土菓子です。
お盆の8月16日に仏壇のお供えとして、農作業の合間のおやつとして、作られます。あまじょっぱくて、つるんとした食感の定番のおやつです。
小麦粉の生地を円形にして薄く伸ばし、黒砂糖、くるみ、味噌で作った餡を真ん中に置き、半分に折り、茹でます。餃子のひだがないような形です。
「じゅね餅、串もち」
「じゅね餅、串もち」についてはこちら ↓↓↓

「べこもち」
「べこもち」は、青森県下北地方の伝統菓子です。
端午の節句に子供の成長を願って、もち米とうるち米の粉と砂糖を混ぜて蒸しあげて作られます。金太郎飴のように、どこを切っても断面に綺麗なお花が出てくるお餅です。お花の種類は、端午の節句の頃に青森で咲くお花のようです。ちなみに、この辺りは地域により端午の節句は、月遅れの6月5日になるそうです。
地域のお母さんたちが作っているものなので、お店などはありませんが、こちらからお取り寄せはできます。↓↓↓

岩手県の有名な和菓子
「岩手県の有名なお菓子」についてはこちら ↓↓↓

宮城県の有名な和菓子
仙臺だんご いち福 「だんご」
宮城県仙台市。昭和61年(1986年)創業。
「だんご」は、しょうゆ、あん、ずんだなどの種類があり、丸い団子ではなく、長い5本の団子生地に串を刺して切ってあるタイプです。
松島こうれん本舗 紅蓮屋心月庵「松島こうれん」
宮城県宮城郡松島町。鎌倉時代の嘉歴2年(1327年)創業。
「松島こうれん」は、米菓で、上白糖入り、還元麦芽入り、和三盆入り、藻塩入り、沖縄黒糖入りなどの種類があります。
菓匠三全「萩の月」
宮城県仙台市。1947年創業。
「萩の月」は、カステラ生地でカスタードクリームを包んだもの。萩は宮城県の県花です。
「萩の月」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

白松がモナカ本舗「白松が栗ヨーカン」
宮城県仙台市青葉区。昭和7年創業。個性的な店名に加え、個性的な商品名が、一度食べたら忘れられなくなるお店です。
「白松が栗ヨーカン」は、宮城県加美町にある自社栗園で栽培された栗を使い作られています。サイズは、超大型、大型、中型があります。
「白松が栗ヨーカン 中型」と「モナカ 中型」のセットを、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

丸森町の「ころ柿」
和菓子店の商品ではありませんが、宮城県伊具郡丸森町で作られている大きくて甘い「ころ柿」が有名です。
「丸森町のころ柿」についてはこちら ↓↓↓

山形県の有名な和菓子
清川屋「笹巻」
山形県鶴岡市。1668年(寛文8年)創業。
「笹巻」については、下記をご覧ください。
清川屋さんのもちもちな「笹巻」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

「ささまき 笹巻き」
「笹巻き」は、山形県に伝わる伝統料理です。山形県の春の風物詩です。
「笹巻き」は、「ちまき」の一種です。
6月が笹の葉の旬となり、どこの家庭でも作られます。笹の葉は、丸まっているものよりも、開いたものが良く、スゲで縛り結びます。
「笹巻き」は、笹の葉をポケット状にたたみ、餅米を入れ茹でたものです。具はなく、モチモチした白いお餅のような食感で、青きな粉と黒蜜をかけて食べたり、納豆をのせて食べたりします。笹の葉の香りが爽やかです。
ちなみに、南庄内地方だけは、黄色い笹巻きになります。もち米を灰汁水(灰を浸した水)に一晩浸け込み、笹の葉で包み茹でると、黄色くなります。食感は、プルンプルンの黄色いゼリーや水羊羹のような感じです。こちらも青きな粉や黒蜜をかけて食べます。
この南庄内地方の黄色い笹巻きは、鹿児島や熊本などで端午の節句の際に食べられる「灰汁巻」がルーツなのではないかと言われています。これは、加藤清正が関係しているといわれています。加藤清正は大名時代に熊本城を築き、長年熊本で過ごしました。その後息子である加藤忠広が庄内地方に配流されています。このことから、竹の皮で巻く灰汁巻が南庄内地方に伝わり、竹の皮が採れなかったので、豊富に採れた笹の葉で作るようになり、さらに灰汁で浸けるのが大変なので、それがなくなったもち米だけで作るタイプが山形県内に伝わったのではないかと言われています。
山形の「いとこ煮」
山形県の庄内地方で食べられています。
小豆を水だけで煮たものを炊飯器の中に入れ、もち米、砂糖、塩を入れて炊くだけ。どろどろでとろんとした料理でもありおやつでもあります。
「みそもち 味噌餅」
山形県の置賜地方の伝統的な郷土のおやつです。餅菓子。
もち米を搗きながら、味噌、砂糖、ごま、くるみなどを入れたお餅です。
青豆を入れるところもあるようです。
福島県の有名な和菓子
「福島県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

栃木県の有名な和菓子
若山商店「御栗(おくり)」
栃木県宇都宮市。
「御栗」は、栗羊羹のような形ですが栗羊羹ではなく、栗きんとんに近いお菓子です。栗そのものの風味を味わえる一品です。
茨城県の有名な和菓子
亀じるし本店「梅ようかん」
茨城県水戸市。嘉永5年(1852年)創業。
「梅ようかん」は、白餡に砂糖、水飴、梅シロップ、寒天を練り上げて作られています。
1887年に「梅ようかん」の前身である「ネリ梅」を作ったのが始まりとされ、1906年には「梅ようかん」と改名され、100年以上愛されている羊羹です。
丸三老舗「極純栗羊羹」
茨城県鹿嶋市。文政5年(1822年)創業。
「極純栗羊羹」は、茨城県岩間市の大きな栗がゴロゴロ入っています。
残念ながら、「極純栗羊羹」のお取り寄せはありませんでしたが、丸三老舗さんの代表銘菓「常陸風土記」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

千葉県の有名な和菓子
なごみの米屋「極上大棹羊羹 栗」
千葉県成田市。成田山表参道。明治32年(1899年)創業。
「極上大棹羊羹 栗」は、栗がまるごと入っています。1棹800g。
「極上大棹羊羹 栗」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

埼玉県の有名な和菓子
阿左美冷蔵 金崎本店「かき氷」
埼玉県秩父郡皆野町。明治32年(1890年)創業の天然氷製造所が営むかき氷店。
「かき氷」は、ふわふわの天然氷が味わえます。
いけだ屋「こだわりの炭火手焼 匠」
埼玉県草加市。慶応元年(1865年)創業。
「こだわりの炭火手焼 匠」は、草加近郊の厳選されたうるち米をセイロで蒸し、天日干しして、備長炭で1枚1枚丁寧に手焼きした逸品です。
菓匠花見「白鷺宝(はくろほう)」
埼玉県さいたま市。
「白鷺宝」は、ミルクコーティングされた餡玉。餡の種類が、小豆、抹茶、紫芋、さくら、黄味、胡麻、紅茶、チョコレートと多彩。
「白鷺宝」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

むら山「栗羊羹」
埼玉県春日部市。
「栗羊羹」は、厳選した大粒の丹波産を3日間丁寧に煮込んだマロングラッセ入りの贅沢な栗羊羹です。1棹480g。

東京都の有名な和菓子
「東京都の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

神奈川県の有名な和菓子
ういろう「ういろう」
神奈川県小田原市。お薬と和菓子を販売しています。
新潟県の有名な和菓子
新潟県長岡市は、茶人大名の城下町で、有名な和菓子が多い地域です。
右門明治堂「笹団子」
新潟県長岡市。「明治堂」として昭和初期創業。「右門明治堂」となったのは、昭和43年。
「笹団子」は、地元新潟のこしひかりを使い、柔らかくもっちりとした甘さ控えめの笹団子です。
「笹団子」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

越乃雪本舗大和屋「越乃雪」
新潟県長岡市。
「越乃雪」は、日本三大銘菓のひとつ。日持ちする干菓子。打ち物。口の中に入れると淡雪のように消えてしまう繊細で儚いお菓子。新潟産のもち米の寒ざらしに和三盆糖を配合し、固めた打ち物。江戸・安政年間に作られました。
残念ながら、「越乃雪」のお取り寄せはありませんでしたが、越乃雪本舗大和屋さんの洋なしのプリンをこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

小竹製菓「笹だんごパン」
新潟県上越市。大正13年(1924年)創業。
「笹だんごパン」は、パンの中に笹だんごが入っているものです。手を汚さずに食べることができ、時間が経っても団子はもちもち。トースターで焼くと美味しい。バターをつけるともっと美味しくなります。
通常の笹だんごは、うるち米ともち粉で作られますが、笹だんごパンはもち粉100%で作られているので、もちもち感が損なわれません。
高橋孫左衛門商店「翁飴(おきなあめ)」
新潟県上越市。寛永元年(1624年)創業。日本最古の飴屋。
「翁飴(おきなあめ)」は、水飴に寒天を混ぜた、ねっとりしたねっとりしたやわらかな弾力のある飴です。
本間屋「ゆずっこ」
新潟県新潟市。文政12年(1829年)創業。
「ゆずっこ」は、生の柚子を使用した蒸し柚餅子で竹皮のパッケージに包まれています。
「ゆずっこ」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

石川県の有名な和菓子
石川県金沢市は、茶人大名の城下町で、有名な和菓子が多い地域で、日本三大菓子処のひとつです。
柚餅子総本家 中浦屋「玉柚餅子(たまゆべし)」
石川県輪島市。1910年創業。明治43年より造り継がれている「丸柚餅子」もあります。
「玉柚餅子」は、柔らかい求肥餅に天然柚子を散りばめ、1口大に丸め、砂糖漬けにしたもの。
「玉柚餅子」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

松葉屋「月よみ山路(栗むし羊羹)」
石川県小松市。嘉永5年(1852年)創業。
「月よみ山路」は、栗が丸ごと入った栗むし羊羹のタイプと味噌とくるみの入ったタイプがあります。竹の皮に包まれ、葛を加えて蒸し上げてある絶品の商品です。
森八「長生殿(ちょうせいでん)」
石川県金沢市。初代は酒造業を営み、二代目が寛永2年(1625年)に菓子業を創業。明治に入り「森八」と改名しました。金沢のひなまつりに欠かせない「金華糖」も有名です。
「長生殿」は、前田利家が豊臣秀吉に献上した打ち菓子を原型として、三代目が作ったもの。日本三大銘菓のひとつ。森八の代表銘菓です。日持ちする干菓子。落雁。北陸産のもち米と阿波徳島の和三盆糖で作られています。

福井県の有名な和菓子
夏に人気の水羊羹ですが、福井県では11月から3月まで「冬の風物詩」として水羊羹を食べる風習があります。
水羊羹を販売するお店は福井県内に100店舗以上あり、お店によって味が違います。そのほとんどが、1枚流しと呼ばれ、箱などの入れ物に流されて1枚状になった水羊羹を自分たちで切って食べるようになっています。
水羊羹の材料は、黒砂糖、粗糖(ザラメ・精製前の砂糖)、こしあん、寒天(羊羹の半分)、水で作られます。火にかけ、炊き上がった水羊羹の寒天とあんこが分離しないよう、40~50分間常にかき混ぜながら緩やかに冷まします。冷えてくると段々重くなってきてずっしりとしてきて固まります。
福井県で水羊羹が食べられるようになったのは、江戸時代、年末に丁稚奉公から福井に戻る時に働き先から持たされた羊羹を甘いものが貴重な時代だったので、水羊羹に作り直したのが始まりとされます。また、冷蔵庫がなかった時代に、夏はすぐにダメになってしまうため、保存が効く冬に食べるようになったとも言われています。
この福井県の「冬の風物詩」である水羊羹には2種類あり、福井県の東側にある福井市や越前町では、厚さが薄めで柔らかめな「水羊羹」が作られています。逆に福井県の西側にある大野市や小浜市などでは、厚さが厚く、水羊羹よりも硬めな「丁稚羊羹」が作られています。それぞれお店さんによってみんな違うので、食べ比べても楽しいかもしれません。
伊勢屋「亥の子餅」
福井県小浜市。
天保元年(1830年)創業。
「大福」や「くずまんじゅう」も有名。
「亥の子餅」は、求肥生地に小豆が練り込まれています。中央に栗餡、その外側にこし餡、そして求肥に包まれます。小豆色の生地で、可愛いピンク色をしています。
残念ながら、「亥の子餅」のお取り寄せがありませんでしたが、伊勢屋さんの「栗きんとん大福」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

えがわ「水羊かん」
福井県福井市。昭和12年(1937年)開業。
「えがわの水羊かん」は、水羊かんではありますが、冬限定(11月~3月)となります。冬の風物詩として地元で愛される味です。黒砂糖の優しい香りと上品な甘さが人気です。
久保田製菓「久保田の水羊かん」
福井県福井市。昭和26年(1951年)創業。
「久保田の水羊かん」は、水羊かんではありますが、冬限定(11月~3月)となります。冬の風物詩として地元で愛される味です。
「久保田の水羊かん」を、冬限定のお届けとなりますが、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

松岡軒「羽二重餅」
福井県福井市。
明治30年(1897年)創業。「羽二重餅」発祥のお店。
「羽二重餅」は、添加物を控え、素材から引き出されたやさしい味わいが特徴。
「羽二重餅」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

今庄の「つるし柿」
和菓子店の商品ではありませんが、福井県南越前町今庄でいぶして作られている「つるし柿」が有名です。
今庄は、豪雪地帯で晴れる日が少なく、干し柿を外で干せず、囲炉裏の上で柿を干していたのがきっかけで、いぶすようになったそうです。
「今庄のつるし柿」についてはこちら ↓↓↓

長野県の有名な和菓子
「長野県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

山梨県の有名な和菓子
栄月製菓「厚焼木の実煎餅」
山梨県大月市。
「厚焼き木の実煎餅」は小麦粉を原料とする甘味せんべい。山椒の豊かな風味と硬さが特徴。生地を3回重ねて厚焼きにして、1枚1枚手焼きしています。
瓦屋「シャインマスカット豆大福」
山梨県南アルプス市。
昭和46年(1971年)創業。
「シャインマスカット豆大福」は、シャインマスカットがまるごと1個入った豆大福です。その日の朝に手作りされる新鮮なおいしさが味わえます。あんこも手作りです。シャインマスカットの時期のみ。
松月堂「栗せんべい」
山梨県南巨摩郡富士川町。
明治32年(1899年)創業。
「栗せんべい」は、山栗の美味しさを詰め込んだ栗せんべいです。栗せんべいは、このお店が発祥と言われています。
「栗せんべい」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

静岡県の有名な和菓子
「静岡県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

愛知県の有名な和菓子
「愛知県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

三重県の有名な和菓子
「三重県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓
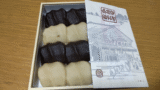
岐阜県の有名な和菓子
「岐阜県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

滋賀県の有名な和菓子
とも栄菓舗 「琥珀糖・MⅠO」
滋賀県高島市。昭和7年創業。
「MIO」は、果実のゼリーを寒天で包んだ琥珀糖。地元産アドベリーという果実とブルーベリーの味があります。見た目も宝石のように可愛い和菓子。
和た与 「でっち羊羹」
滋賀県近江八幡市。幕末の文久3年(1863年)創業。
「でっち羊羹」は、和た与が発祥とされています。小豆餡と小麦粉を合わせ、竹の産地であったことから、竹の皮に包んで蒸したものが「でっち羊羹」です。
京都府の有名な和菓子
「京都府の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

大阪府の有名な和菓子
粟玄「和洋」
大阪府大阪市住吉区上住吉。昭和25年(1950年)創業。
「和洋」は、アーモンドをコーヒー味の飴でからめ、粟おこしの技法で固めたサクサクとしたお菓子です。
庵月(あんげつ)「栗蒸し羊羹」
大阪府大阪市中央区。慶應年(1868年)「常盤堂」という名で神戸に創業。第二次世界大戦後、大阪に移転し、「庵月」という名になりました。
「栗蒸し羊羹」は、栗が2、羊羹が1の割合で、栗がごろごろ入っています。
本家小嶋「芥子餅(けしもち)」
大阪府堺市堺区。室町時代の天文元年(1532年)創業。
「芥子餅(けしもち)」は、こしあんを包んだ軟らかいお餅と小さな芥子(けし)の実の食感がクセになります。堺出身の千利休も愛したという芥子餅。千利休により全国に知れ渡りました。
岡山県の有名な和菓子
岡山県の四大銘菓として、「吉備団子」「大手まんぢゅう」「調布」「つるの玉子」があります。
大手饅頭伊部屋「大手まんぢゅう」
岡山県岡山市。1837年創業。
「大手まんぢゅう」は、日本三大まんじゅうのひとつ。
「大手まんぢゅう」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

つるの玉子本舗 下山松壽軒「つるの玉子」
岡山県岡山市北区。明治20年(1887年)創業。きびだんご、調布もおすすめです。
「つるの玉子」は、紅白のマシュマロ饅頭です。外側がマシュマロで中が黄味餡になっており、卵に見立てているそうです。
「つるの玉子」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

天任堂「ゆべし」
岡山県高梁市。江戸時代創業。
包みゆべし、切りゆべし、結びゆべし、丸ゆべし、みそゆべしなど、たくさんの形の種類のゆべしを販売されています。
「包みゆべし」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

広島県の有名な和菓子
にしき堂「生もみじ」
広島県広島市東区。昭和26年(1951年)創業。
「生もみじ」は、もちもちしっとりとした、生菓子風のもみじ饅頭です。
「生もみじ」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

尾道柿園の「干し柿」
和菓子店の商品ではありませんが、広島県尾道市にある「尾道柿園の干し柿」が有名です。
「尾道柿園の干し柿」についてはこちら ↓↓↓

島根県の有名な和菓子
「島根県の有名な和菓子」についてはこちら ↓↓↓

香川県の有名な和菓子
二見屋(ふたみや)「竹林糖」
香川県さぬき市志度地区。
「竹林糖」は、黒砂糖を煮詰め、生姜を入れた板チョコのようなサクサクしたお菓子です。生姜の入った黒砂糖を煮詰め、とろっとしてきて泡がなくなったところで、型に入れて固めます。お菓子として食べるだけでなく、豚の角煮などに入れたりもします。
寳月堂(ほうげつどう)「栗饅頭」
香川県丸亀市。大正6年(1917年)創業。
「栗饅頭」は、昔懐かしい味の饅頭。1個づつ小箱に入っています。
徳島県の有名な和菓子
岡萬本舗「お堰の小舟」
徳島県西郡石井町。明治35年創業。代表銘菓「バターサンド」もおすすめ。
「お堰の小舟」は、いちじくジャムと餡、生地には阿波和三盆糖を使用し、セミドライのいちじくがのった和菓子。
残念ながら、「お堰の小舟」はお取り寄せがありませんでしたが、「バターサンド」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

愛媛県の有名な和菓子
一六本舗「一六タルト」
愛媛県松山市。
「一六タルト」は、愛媛県産の柚子とこしあんをやわらかいスポンジで巻いた風味豊かなお菓子です。
タルトは、1649年ポルトガル船が長崎に来た際に、松平定行公が異人館でフランスのタルトレットという南蛮菓子をもてなされ、それを地元松山に伝えたとされます。この頃のタルトレットは、ジャムが巻かれていたようで、こしあんにすることを定行公が独自に考案し、地元愛媛の柚子を入れ、現在の形へとなったそうです。
この頃に甘い餡を作ることができたのは、定行公の奥様が薩摩の島津家の出身であったことから交流が盛んであったことからとのこと。
「一六タルト」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

高知県の有名な和菓子
渋谷食品「芋けんぴ」
高知県高岡郡日高村。昭和34年(1959年)創業。
「芋けんぴ」は、国産の黄金千貫を使用し、昔ながらの味を引き出しています。
「芋けんぴ」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

福岡県の有名な和菓子
かさの家「梅が枝餅(うめがえもち)」
福岡県太宰府市。大正11年創業。
「梅が枝餅」は、太宰府天満宮の名物です。生地はもち米とうるち米から作られており、中に小豆餡を入れ、梅の刻印が入った鉄板で焼いた焼き餅です。大宰府に配流となった菅原道真に、近くの尼が好きだった餅を梅の枝につけて差し上げたことが始めまりと言われているそうです。
「梅が枝餅」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

にわかせんべい本舗 東雲堂「二〇加せんべい(にわかせんべい)」
福岡県福岡市博多区。明治39年(1906年)創業。
「二〇加せんべい」は、小麦粉、砂糖、そしてたっぷりの博多名物の鶏卵から作られている優しい味の甘いせんべいです。
形は、仮面の半分をいう「半面」のデザインとなっています。これは、古くからなじまれている郷土芸能にお菓子を結びつけたものです。
廣久葛本舗「久助葛」
福岡県朝倉市。文政2年(1819年)創業。
「久助葛」は、天然純国産本葛100%使用の保湿性に優れ、粘りがあり、喉押しの良い本葛です。葛切りなどにご利用いただけます。
葛湯などの販売もされています。
明月堂「博多通りもん」
福岡県福岡市博多区。1929年創業。
「博多通りもん」は、白餡のおまんじゅうです。生地にはバター、ミルク、卵を使った西洋和菓子をコンセプトに作られたお菓子です。
「博多通りもん」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

佐賀県の有名な和菓子
天山本舗「YOU CAN(ようかん)」
佐賀県小城市。昭和27年創業。
「YOU CAN」は、「君ならできる!」というキャッチフレーズの羊羹です。
村岡総本舗「小城羊羹」
佐賀県小城市。明治32年(1899年)創業。
「小城羊羹」は、江戸時代から続く伝統の羊羹です。種類は、小倉、紅煉、本煉、きびざとう、抹茶、青えんどうがあります。他にも、カシューナッツ羊羹、シベリア、丸ぼうろなどがあります。
店舗隣には、村岡総本舗が運営する「羊羹資料館」があります。入場は無料です。
長崎県の有名な和菓子
松翁軒「渋皮栗寄せの抹茶カステラ」
長崎県長崎市。天和元年(1681年)創業。「長崎カステラ」の名店。
「渋皮栗寄せの抹茶カステラ」は、8月下旬~1月中旬の期間限定品です。抹茶のカステラの中に、栗の渋皮煮が丸ごと入っています。
「渋皮栗寄せの抹茶カステラ」は、お取り寄せがありませんでしたが、松翁軒さんの「カステラの3種セット」をこちらからお取り寄せができます。↓↓↓

平戸蔦屋「カスドース」
長崎県平戸市。文亀2年(1502年)創業。
「カスドース」は、1550年のポルトガル船の来航により広まった南蛮菓子です。「かすていら」を固く焼き、卵黄に浸け、砂糖と水で作った砂糖蜜が沸騰して泡が出てきたら絡め、上からグラニュー糖でまぶしたお菓子です。
熊本県の有名な和菓子
くま純「いきなり団子」
熊本県熊本市中央区。
「いきなり団子」は、素材にこだわり、季節ごとに一番美味しい九州産のさつまいもを使用しています。カットしたさつまいもに粒あんをのせ、もっちり食感の団子で包み蒸しています。1つ1つ手作りで作られています。ミニタイプや、栗入りなどもあります。
開懐世利六菓匠(かわせりろっかしょう)
熊本県熊本市南区川尻にある6件の老舗和菓子店(天明堂、お菓子のいしはら、菓匠たてやま、菓舗梅園、いわもと、菓舗かずさ屋さん)の和菓子職人たちによる和菓子の町おこしの活動のことです。素敵ですね。
宮崎県の有名な和菓子
「ねったぼ」
蒸したさつまいもをつぶし、柔らかいお餅と練り合わせて滑らかにしたもので、きな粉をかけて食べます。
お菓子の日髙「なんじゃこら大福」
宮崎県宮崎市橘通西。昭和26年創業。
「なんじゃこら大福」は、いちご、栗、クリームチーズが入った大福です。口に入らないくらい1つが大きく、1人で1つ食べるのが大変な大きさです。お菓子の日髙さんは、他にも栗が5つも入った「五ツ栗饅頭」や「チーズ饅頭」など、心が愉快になる幸せを呼ぶお菓子がたくさんあります。
マロンハウス(甲斐果樹園)「栗九里」
宮崎県西臼杵郡日之影町。
「栗九里」は、高千穂の日之影栗(ひのかげくり)を100%使用した栗きんとんです。原料は、栗と砂糖のみだけで作られた極上スイーツ。一度食べたら忘れられない味です。
鹿児島県の有名な和菓子
明石屋「軽羹・軽羹饅頭セット」
鹿児島県鹿児島市。安政元年(1854年)創業。
「軽羹・軽羹饅頭セット」は、生地だけの軽羹が好きな方も、餡が入った饅頭になった軽羹饅頭が好きな方も、どちらにも対応できるセットです。自然薯と米の粉と砂糖だけで作られる軽羹は、もちもちとした上質な生地がに人気です。
「軽羹・軽羹饅頭セット」を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

梅木屋「あくまき」
鹿児島県南九州市。昭和3年創業。「薩摩の伝統菓子」を作っておられます。
「あくまき」は、すべて手作業。6時間、鉄釜でゆっくりと煮込んでいます。
「あくまき」だけのお取り寄せがなく、梅木屋さんのこだわりの品のセットがお取り寄せできます。↓↓↓

沖縄県の有名な和菓子
「ぜんざい」
沖縄県の「ぜんざい」は、金時豆を豆が潰れない状態に煮たものを器に入れ、その上に氷をのせたものをいいます。氷には何もかけず、煮た金時豆とその汁と共にいただきます。「かき氷」ではなく、「ぜんざい」と言います。
明日はどんな手仕事する?
こちらの地域別の記事に関しては、まだまだ書き続けたいと思っております。常に更新していきますので、ぜひまた見にいらしてください。
それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
和菓子の関連記事
◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓










コメント