和菓子の材料の「粉」の種類の紹介です。
繊細な味と見た目の和菓子は、作るものによって材料の種類を細かく変えます。ただこの材料の種類が気軽に揃うというわけでもありません。代用できるものもあるかとは思いますので、上手に使いこなしていきましょう。
紹介した材料に載せたそれぞれの商品はお取り寄せができます。わざわざお店まで探しに行かなくても、希少なものも手に入れることができます。クリックして詳細もご覧いただけます。作ってみたいものがあれば、参考になさってみてください。
項目ごとにあいうえお順にしてあります。
米を原料とする粉の種類「米粉(べいふん)」
米を原料とする粉にはさまざまな種類があり、作るお菓子によって使い分けます。
米の粉は大きく分けて、「もち米」を原料とするものと「うるち米」を原料とするものがあります。
総称して「米粉(こめこ)」と呼ばれますが、正式には「米粉(べいふん)」と呼びます。
小麦を使わない米粉を使ったお菓子は、グルテンフリー市場で注目をされています。グルテンとは、小麦に含まれるたんぱく質の一種が水と混ざりできるものです。パンのふわふわした食感やパスタなどのコシのある食感をいいます。アレルギーのある人や小麦をとらない人にはグルテンフリーが必要となります。
「もち米」を原料とする粉の種類
「もち米」は、餅や赤飯などに使われる米。もち米の澱粉は、加熱され糊化すると粘りや弾力、膨張力が非常に強くなります。
いりこ 煎り粉
→「新引粉」をご覧ください。
かんざらしこ 寒晒し粉
→「白玉粉」をご覧ください。
「寒晒し粉」は、昔は寒中に手間暇かけて作られたので、このようにも呼ばれました。
かんばいこ 寒梅粉
もち米から作る粉。
もち米を洗って水につけ、水気を切って蒸してつき、餅にしてごく薄くのばして、半乾きの状態で白いまま焼き色をつけないように焼き、粉末にしたものです。水分を吸収しやすく、つなぎとして使われます。
より細かい「上みじん粉」のことを「寒梅粉」ということもあります。
名前の由来は、寒梅が咲く頃に新米を餅にして粉が作られたことからつけられたとされます。
雲平、桃山、みじん羹、葛焼き、練切、黄味時雨、塩釜、押し物、打ち物などに使われます。
関東では「みじん粉」とも呼ばれます。
「寒梅粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

ぎゅうひこ 求肥粉
→「もち粉」をご覧ください。
じょうなんこ 上南粉
もち米から作る粉。
道明寺粉を、焼き色をつけないように焼き上げて細かく粉砕した粉になります。
押し物に使われます。
「落雁粉」とも呼ばれます。
「上南粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

しらたまこ 白玉粉
もち米から作る粉。
もち米を洗って水につけ、水を切ったあと、水を加えながら石臼で挽き、寒中に何日も水にさらし、沈殿物を乾燥させたもの。もち粉よりも弾力があり、つやがよく仕上がります。
白玉、団子、求肥、蕎麦餅などに使われます。
「寒晒し粉(かんざらしこ)」とも呼ばれます。
「白玉粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓


しんびきこ 新引粉
もち米から作る粉。
もち米を洗い水につけて、水を切って蒸して乾燥した後、粉砕して煎ったもので、上南粉よりも粒子が小さい。
落雁などの押し物、おこし、お料理などでは天ぷらや揚げ物の衣にも使われます。
「煎り粉」「はったい粉」とも呼ばれます。
「新引粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

どうみょうじこ 道明寺粉
もち米から作る粉。
もち米を洗って水につけ、水気を切って蒸し、よく乾燥させた「干し飯(ほしいい・正式な漢字は『糒』)」を粗く挽いたものです。
いろいろな大きさに挽き、一番細かいものを頭道明寺粉(かしらどうみょうじこ)といいます。頭道明寺粉がない場合、「六つ割」「八つ割」という細かいもの(蒸す必要がないと表記されたもの)で代用できます。
1000年前、大阪河内の道明寺でご本尊へのお供えしたご飯のおさがりを天日で干し保存食にした「道明寺糒(どうみょうじほしい)」が道明寺粉の由来とされています。そのことから、道明寺粉は昔は保存食や携帯食として用いられていました。
現在、道明寺粉は、桜餅、みぞれ羹などに使われます。
「道明寺粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

はぶたえこ 羽二重粉
→「もち粉」をご覧ください。
みじんこ 味甚粉 微塵粉
→「寒梅粉」をご覧ください。
もちこ 餅粉
もち米から作る粉。
もち米を水洗いして乾燥させ、製粉したものです。風味がよく、滑らか。製法は「上新粉」と同じ。白玉粉よりも粒が粗い。
花びら餅、練切、求肥などに使われます。
粒子の細かさによって、「求肥粉」「羽二重粉」とも呼ばれます。
「餅粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

らくがんこ 落雁粉
→「上南粉」をご覧ください。
「うるち米」を原料とする粉の種類
「うるち米」とは、主食としている白米のことをいいます。うるち米の澱粉は、粘りや膨張力が弱く、糊化した後の老化が早い。いずれも非加熱で虫がつきやすいため、早めに使い切ることがおすすめです。
かるかんこ 軽羹粉
「軽羹粉」についてはこちら ↓↓↓

じょうしんこ 上新粉
うるち米から作る粉。
うるち米を水洗いして水気をきり、石臼で挽き、ふるい分けてから乾燥させたもの。歯応えがあります。生なので長期保存には向きません。
柏餅、草餅、団子などに使われます。
どんど焼きの団子などは、スーパーでも手に入りやすいこの上新粉を使うことが多くなります。
「どんど焼き」の団子の作り方についてはこちら ↓↓↓

「上新粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

じょうよこ 上用粉 薯蕷粉
うるち米から作る粉。
うるち米を水づけし、水気を切って臼でつき、粉にしてふるい分け、乾燥させたもの。上新粉と製法は同じだが、粒子はさらに細かいので滑らかに仕上がります。
上用饅頭(薯蕷饅頭)、外郎などに使われます。
「薯蕷粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

しんこ 新粉
うるち米から作る粉。
精白したうるち米を水洗いして水切りし、しばらく乾燥させてから製粉したものの総称。
それを乾燥させてからふるいにかけると、少し粗い「新粉(並新粉)」、細かい「上新粉」、更に細かい「上用粉(薯蕷粉)」に分けられます。
にゅうじこ 乳児粉
うるち米から作る粉。
うるち米を熱加工して、製粉したもの。
乳児食、離乳食、重湯などに用いられます。
米以外のものを原料とする粉の種類
いろこ 色粉
着色料として許可されている食用の色粉。水で溶いて薄めて使います。
練切などに使います。
昔からある色粉と違い、ナチュラルな色粉です。こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

うぐいすきな粉
青大豆を煎って粉砕し粉にした、緑が鮮やかなものをいいます。
うぐいす餅などに使います。
「青きな粉」とも呼ばれます。
「うぐいすきな粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

かたくりこ 片栗粉

お花をされる方ならば、「カタクリ」は春に可憐に咲く花として使う方が多いことでしょう。
別名「堅香子(かたかご)」。ユリ科カタクリ属の多年草。花の開花は3月下旬~4月上旬。開花期間は2週間ほどと短い。林に自生。ひっそりと咲いています。花が下を向いて、花びらが上にそるように咲きます。花の色は紫系のピンク。埼玉県の小川町にはカタクリの花の群生地があります。
この「カタクリ」は、鱗茎(根の部分)、若い葉、花までが春の山菜として、古くから食べられています。
鱗茎にはでんぷんが含まれており、古くはこのでんぷんを抽出し、片栗粉として料理のとろみ付けなどに用いられてきました。
本来はこの野草のかたくりの地下茎から採る澱粉ですが、現在の片栗粉は、じゃがいものでんぷんから作られています。
打ち粉に使うと生地につやが出ます。
黄味雲平などに使われます。
「片栗粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

きなこ 黄粉
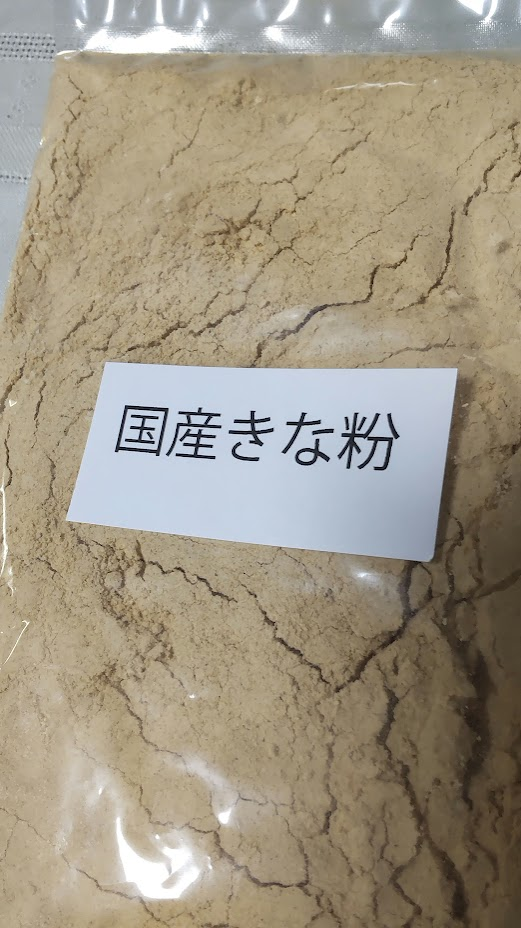
「きなこ」は、煎った大豆を粗挽きにして皮を除き、よく粉砕したものです。良い香りと消化もよく、栄養があります。
湿気を呼ぶので、香ばしいうちに使い切るのがおすすめです。
おはぎや安倍川餅、葛餅、わらび餅などの甘味に使うほか、ヨーグルトなどにもかけて食べます。
毎日でも摂りたい「きなこ」を、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

きょうりきこ 強力粉
小麦粉のひとつ。グルテンの料が多く、硬質小麦から作られています。水をよく吸います。
パン、ピザ、中華麺などに使われます。和菓子にはあまり使われません。
くりこ 栗粉
栗の実を乾燥させて作る「栗粉」。「栗粉」は、日本で採れる和栗からはできず、粘り気のないイタリアやフランスで採れる西欧栗から作られます。
ヨーロッパでは、古代ローマの頃から愛されていた栗。小麦粉が採れない山間部では栗を作り、栗粉にしてたんぱく源を摂っていました。
栗粉自体が甘いので、ケーキなどを作る際には、砂糖は入れずに使います。また、栗粉を炭酸水で溶くと生地がふんわりします。オリーブオイルやドライフルーツを加えるだけで、イタリアのケーキ「カスタナッチョ」ができます。
こおりもち 氷餅
長野県諏訪地方の特産品。餅あるいは餅米の米汁を凍らせてから、寒風に晒して乾燥させた保存食。
和菓子の材料としては、まぶし粉として、崩して菓子にまぶし、餅菓子の乾燥や菓子器への付着を防ぎます。崩し方によって雪や霜、霞などさまざまなものが表現でき、風情を表現できる材料です。
「氷餅」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

こむぎこ 小麦粉
「薄力粉」、「中力粉」、「強力粉」の総称。原料は小麦。小麦の種類により、それぞれ分かれます。和菓子では、「薄力粉」がよく使われますが、「中力粉」と「強力粉」はあまり使われません。
シナモンパウダー
肉桂とも呼ばれるスパイスのひとつ。甘く爽やかな香りと微かな辛味があり、風味付けなどに使われます。
「シナモンパウダー」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

じゅうそう 重曹
炭酸水素ナトリウムの白い粉で、ふくらし粉として使われます。
どら焼きなどに使います。
「重曹」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

すはまこ 州浜粉
浅く煎った大豆や青豆から作られています。
「州浜粉」を使ったお菓子の総称を「すはま」と呼びます。
そばこ 蕎麦粉
蕎麦の実を挽いて粉にしたもの。独特の風味を生かし、蕎麦まんじゅうや蕎麦ぼうろなどに使います。
蕎麦粉は大まかに一番粉、二番粉、三番粉に分けられます。
一番粉は、蕎麦の実の中心にある胚乳の中心部分が主体で、白く甘みが多いですが、蕎麦の香りや風味に欠けます。「更科粉(さらしなこ)」とも呼ばれます。
二番粉は、残りの胚乳と胚芽の一部分が主で、蕎麦独特の香りや風味が強く、栄養価も高くなります。
三番粉は、さらに残りの胚乳と胚芽に甘皮の一部が入ります。香りや風味が濃く、栄養価も高いのですが、食感が劣るとされています。
「蕎麦粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

ちゅうりきこ 中力粉
小麦粉のひとつ。グルテンは強力粉より少なく薄力粉よりも多い中間質の小麦からつくられています。
うどんや餃子の皮などに使われます。和菓子には、あまり使われません。
はくりきこ 薄力粉
和菓子にもよく使われる小麦粉のひとつ。グルテンが少なく、粘りがあまりない軟質小麦から作られます。湿気のない新しいものをよくふるって使います。水をあまり吸いません。
かりんとうなどお菓子全般や天ぷら、お好み焼きなどに使われます。
「薄力粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

はすこ 蓮粉
蓮粉とは、レンコンから作る澱粉で葛粉やわらび粉とは違った風味や食感になります。蓮粉から作る「蓮粉餅」は、蒸してから火にかけて充分に練ると、なめらかでコシのある状態になります。
はったいこ はったい粉
大麦を煎って粉にしたもの。色は灰褐色をしています。「麦こがし(という粉)」「麦香煎」とも呼ばれます。
「麦落雁」「麦こがし(というお菓子)」などに使います。
ベーキングパウダー
小麦粉を使うものに使います。粉類と一緒にふるい、均一に混ぜて使うとよい。
最近では、小分けされているものが助かります。
「ベーキングパウダー」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

ほんくずこ 本葛粉
葛についてや、「本葛粉」、葛を使った和菓子についてはこちら ↓↓↓

ほんわらびこ 本蕨粉
春の山菜であるわらびの地下茎を砕き、白粉を取り除き、精製した澱粉。「本わらび粉」は、純粋なわらび粉が原料です。本わらび粉100%で作るとわらび餅が黒くなります。それが本当の「わらび餅」の色です。特有の粘りがあり、弾力があります。近年では生産量が減って希少品になっています。

ちなみに、「わらび粉」がわらびの地下茎の澱粉からできているのに対し、「わらび餅粉」は甘藷(さつまいも)の澱粉からできています。
「わらび餅粉」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

「わらび餅」を作ってみなくなった方はこちら ↓↓↓

まっちゃ 抹茶
特別な栽培法のお茶の若芽を石臼で細かく挽いたもの。
「抹茶・抹茶菓子」についてはこちら ↓↓↓

水まんじゅうの素
葛粉と寒天をほどよくブレンドした粉は、プルプルの舌触りの水まんじゅうが手軽に作れる便利な素です。
「水まんじゅうの素」は、こちらからお取り寄せできます ↓↓↓

もちとり粉
お餅搗きをする際に、お餅が手や板などにつかないようにまぶす粉です。もちとり粉を使うことで、お餅を小分けしたり、丸めやすくしたりします。
明日はどんな手仕事する?
粉の種類は多く、特に米を原料とする種類が多く、この使い分けが難しいです。その粉がないからあるもので作ろうなんてことをしてしまうと、系統が同じものならできないことはないのですが、違う系統のものを使ってしまうと、違うものが出来上がってしまったりします。
粉の作り方自体、工程の微妙な違いだけなのに、お菓子になると違うものができてしまうとは思えないほど、見た目には変わりがないものばかりです。
ただその違いを間違えてしまうと本物ができないということになります。
粉の種類は、大切です。微妙な違いもなるべく、その粉を使うのがよいでしょう。
何度か作っていくと、材料に拘ってみたくなるかと思いますので、そしたら今回の記事のように、いろいろな材料も揃えてみてください。
みなさまの和菓子作りが楽しくなることを願っております。
それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
和菓子の関連記事
◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子⑧和菓子の用語」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓










コメント