もっと知りたい「桃」について
桃の産地
◆山梨県笛吹市
◆愛知県豊田市の「猿投(さなげ)の桃」
◆岡山県
◆香川県丸亀市飯山町の「飯山(はんざん)の桃」
桃全体の旬
6月下旬~9月下旬。
各品種の旬は、1ヶ月以内のものも多く、すぐに終わってしまいますので注意が必要です。
桃農家さんも、旬がずれるようにいくつかの品種を栽培しています。
桃の選び方
収穫するものや販売されているものを含めた桃の選び方としては、下記のものが良いでしょう。
◆色付いているもの。赤くなる品種は、赤さが濃く、赤い面が多いもの。
◆「果点(かてん)」と呼ばれる斑点のあるもの。赤い桃には白い斑点が、白い桃には黒い斑点が出ます。これは桃からの美味しいサインです。
◆お尻の部分が左右均等で、割れ目の食い込みが深いもの。
◆傷のないもの。
甘くて大きな桃にする栽培方法
桃の樹高

桃の木は、高くても3メートルほどです。
桃は、目の高さの位置から、高くでも短い脚立に乗れば採れる位置になっていました。

果実の木は、上に伸ばさず、横に広げるように育てると言いますが、まさに、こんなに低いところから3方に分かれていました。
桃の葉

長さ10センチほど、幅3センチほどの細長い葉です。
桃の花の摘花
桃の栽培で一番難しいのが、摘花と言われています。3月下旬頃に1本の木に花が1万個咲くと言われています。そのうちの100個を残し、次の段階で30個にし、実になりそうになってきたら1本の枝に10個のみを残し、全部落とす。実が少し大きくなったら3個にし、最終的に1個だけを育てると言われています。
桃の袋掛け
桃の実には、2枚重ねの袋を掛け、1枚は遮光できるものになっていて、光を当てないようにします。大きさが収穫できるくらいまでになったら、遮光する袋を取り、日が当たる白い袋にします。10日間太陽を当て、赤身が半分くらいまでついたら収穫します。

色付く前の桃です。
桃の収穫時期
6月下旬から9月頃まで、いろいろな品種がなり続けます。
桃の収穫方法
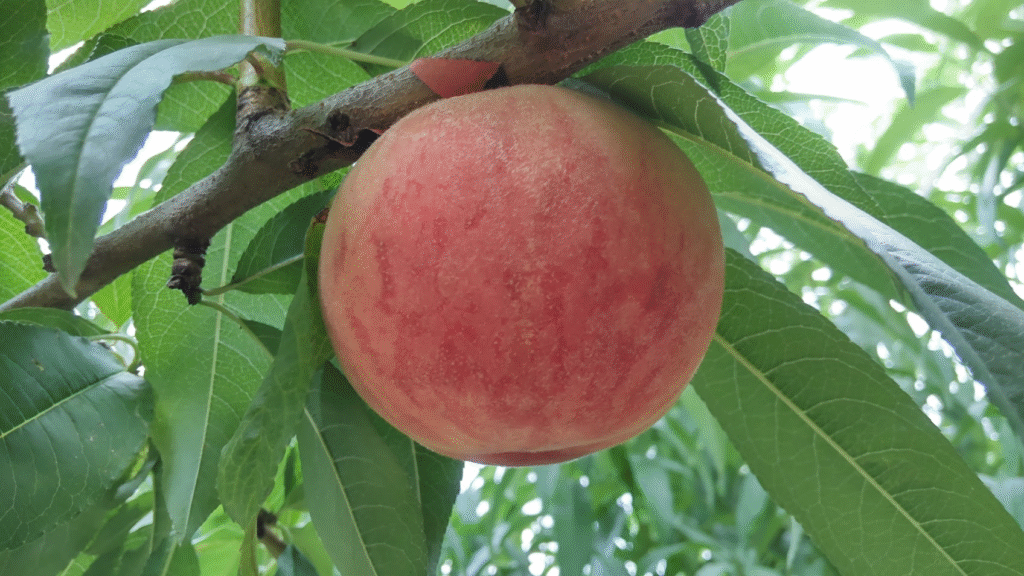
桃は、目の高さのものから、短い脚立に乗れば採れるところになっています。
力強く触ることなく、優しく触る程度に茎(ヘタ)を折るだけで収穫することができます。茎をねじったりしなくても簡単に採ることができます。
桃の保存方法
桃は追熟しないといわれています。ただ追熟はしませんが、その桃が熟される分は甘くなります。なるべく傷をつけないように、ヘタの部分を下にして、蒸されないようにして、キッチンペーパーなどで包み常温で保管するのが良いでしょう。
桃の賞味期限
採り立てで、傷などがなければ4~5日は保存可能です。傷があるものや、収穫してから何日経っているかがわからないスーパーなどで販売されているものは、できるだけ早めにいただきましょう。
もっと知りたい「桃の食べ方」

桃は冷やす?冷やさない?
桃を食べるのに、冷やすか冷やさないかは、好みだと思います。
冷たい方がひんやりして美味しいですし、冷やさなければ甘みを強く感じることができます。
ただ、冷やすようであれば、長時間冷やすのではなく、食べる1時間前に冷蔵庫の野菜室に入れるのが良いでしょう。桃は追熟しないとはいいますが、常温で保存しておくと熟されて甘くなります。食べる直前に冷やすようにしましょう。逆に冷やし過ぎるのは、よくありません。
桃の美味しい皮のむき方
桃は皮をむくのが当たり前のように思えますが、桃の産地の方は、皮ごと食べます。皮をむきません。皮に近い部分が一番甘いからです。新鮮なものであれば、食べ慣れていない方でも抵抗なく食べることはできます。
ただ、やはりむきたいという方は、熟し加減にもよります。
◆熟していないようであれば、皮もむきにくいので包丁で皮をむくのが良いでしょう。
◆熟しているようでしたら、手で簡単にむけます。
桃の美味しい切り方
切り方もいろいろな切り方があります。お好きな方法で良いと思いますが、むき方同様、熟し加減で変えるのが無駄なく食べられる気がします。
◆柔らかくなく熟していない場合は、1個を8等分にして、包丁を種のところまで入れて、「くいっ」ともちあげて種からとり、皮をむく。
◆多少柔らかく熟してきている場合は、半分に切ってから皮をむき、種を包丁で取り出して、食べやすい大きさに切る。
◆かなり柔らかく熟している場合は、1個のまま皮をむき、適当な大きさに切っていき、種を残す。
桃のメニュー
◆コンポート
◆ジャム
◆ゼリー
◆スムージー
◆生ハムを巻いたサラダ
もっと知りたい「桃の品種」

桃の品種は、100種類以上あると言われています。
桃の品種名があいうえお順になっております。
あかつき
◆産地
香川県丸亀市阪南地区、山梨県など。
◆旬
7月上旬~8月中旬。
◆外皮色
濃いピンク。
◆食感・硬さ
果肉が硬い。
◆甘さ
甘みが強い。
あさまはくとう 浅間白桃
◆原産
山梨県。
◆産地
山梨県
◆歴史
1974年に山梨県で発見された品種。
◆交配
「高陽白桃」の枝変わり品種。
◆旬
7月下旬~8月上旬。
◆外皮色
ピンク。
◆果汁
とても多い。
◆甘さ
甘い。
あまあまさんさん 甘甘燦燦
◆産地
福島県、山梨県など。
◆系統
白桃系。
◆交配
「川中島白桃」と「夕空」の交配品種。
◆旬
9月上旬~9月下旬。晩生品種。
◆サイズ
約450gもある超大玉品種。
いちのみやはくとう 一宮白桃
◆産地
山梨県。
◆旬
7月下旬~。
おうきひ 黄貴妃
◆旬
8月下旬~9月。
◆サイズ・重さ
300~350gある大玉。
◆外皮色
黄色
◆果肉
黄色
◆食感・硬さ
やや硬め。
◆甘さ
甘みは強く、酸味は控えめ。
◆香り
芳醇な香りがします。
おうごんとう 黄金桃
◆産地
山梨県など。
◆旬
8月上旬~9月。
◆外皮色
黄金色。
◆食感・硬さ
柔らかめ。
おかやま夢白桃
◆旬
7月下旬~8月中旬。
◆外皮色
白。
◆食感・硬さ
柔らかい。
おどろき
◆旬
7月下旬~8月下旬
◆外皮色
濃いピンク。
◆食感・硬さ
硬い。
かのういわはくとう 加納岩白桃
◆原産
山梨県山梨市加納岩地区。
◆産地
山梨県山梨市。
◆系統
白桃系。
◆交配
「浅間白桃」の枝変わり品種。
◆歴史
1976年に発見され、1983年に品種登録。
◆旬
6月中旬~。
かわなかじまはくとう 川中島白桃
◆別名
「桃の王様」
◆産地
長野県、山梨県など。
◆歴史
昭和30年代(1955~1965年頃)、長野県長野市川中島町で栽培が始まりました。
◆旬
8月中旬~9月上旬。
◆サイズ
大玉。
◆外皮色
濃いピンク。
◆食感・硬さ
シャキシャキとした食感で硬め。
◆甘さ
甘い。糖度が高い。
◆食べ方
皮ごと食べると美味しい。
くにか 紅錦香
◆原産
長野県
◆産地
長野県、山梨県など。
◆交配
「野池白桃」の枝変わり品種。
◆旬
8月中旬~。
さくらはくとう さくら白桃
◆旬
8月下旬~9月。
◆外皮色
濃いピンク。
さちあかね 幸茜
◆原産
山梨県。
◆産地
山形県、福島県、山梨県など。
◆交配
「山一白桃」の枝変わり品種。
◆旬
8月下旬~。晩生品種。
◆サイズ
1個400gにもなる超大玉。
しみずはくとう 清水白桃
◆別名
「桃の女王」
◆原産
岡山県岡山市芳賀清水地区。
◆産地
岡山県、和歌山県など。
◆歴史
1932年に偶発実生した品種。
◆名前の由来
誕生した地名の清水地区より付けられました。
◆旬
7月下旬~8月中旬。
◆外皮色
乳白色。
◆食感・硬さ
とても柔らかい。
◆果汁
豊富。
◆甘さ
とても甘い。
◆特徴
白桃の代表品種。
せいおうぼ 西王母
◆別名
「幻の桃」 希少性が高いことから。
◆原産
福島県。
◆産地
福島県、山梨県など。
◆名前の由来
古代中国の神話に登場する女神の名前から付けられました。
◆旬
8月下旬~9月。晩生品種。
◆サイズ
大玉。
◆外皮色
ピンク。
◆果肉
白桃。
◆食感・硬さ
柔らかめ。
◆果汁
豊富。
◆甘さ
糖度が高い。
なつおとめ
◆産地
香川県丸亀市阪南地区、山梨県など。
◆旬
7月中旬~下旬に出荷される品種。
◆甘さ
酸味が少なく、甘みが強い。
なつっこ
◆産地
香川県丸亀市阪南地区、山梨県など。
◆旬
7月中旬~8月中旬に出荷される品種。
◆外皮色
濃いピンク。
◆食感・硬さ
硬め。
◆甘さ
酸味が少なく、甘みが強い。
はくほう 白鳳
◆産地
山梨県など。
◆旬
7月中旬~下旬
◆外皮色
白。
◆食感・硬さ
柔らかい。
はつひめ
◆旬
7月中旬
◆外皮色
ピンク。
◆食感・硬さ
柔らかい。
はなよめ
◆原産
山梨県笛吹市原産。
◆産地
山梨県笛吹市など。
◆旬
6月中旬~7月中旬に出荷される品種。
◆サイズ
サイズは小さい。
◆外皮色
外皮色はピンク。
◆食感・硬さ
柔らかい。
◆特徴
笛吹市ではシーズン最初に採れる品種。
ばんとう 蟠桃
◆原産
中国原産。
古代中国では、不老不死の果実として神話や伝説に出てくるほど有名な品種。
◆産地
福島県、和歌山県、山形県など。
◆旬
7月下旬~8月中旬。
◆形
扁平型。日本の桃にはない形。
◆外皮色
濃いピンク。
◆甘さ
甘みが強い。
◆特徴
種が小さく、可食部が多いのが特徴。
◆「蟠桃」の苗を、こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

ひかわはくほう 日川白鳳
◆産地
香川県丸亀市阪南地区。
◆旬
6月中旬~7月下旬に出荷される品種。
◆サイズ
大きい。
◆外皮色
濃いピンク。
◆食感・硬さ
柔らかくてみずみずしい。
◆甘さ
とにかく甘い。
べにくにか 紅くにか
◆原産
長野県。
◆産地
長野県、山梨県など。
◆交配
「紅錦香(くにか)」の早生を」選抜育成してできた品種。
◆旬
8月上旬~。
やまと 大和
◆原産
奈良県
◆産地
奈良県、山梨県など。
◆系統
白鳳系。
◆旬
7月中旬~。
◆外皮色
淡い紅色。
◆食感・硬さ
固め。しっかりとした歯ごたえ。
やまとはくとう 大和白桃
◆別名
「伝説の白桃」
◆産地
岡山県の一部の地域のみで栽培。
◆系統
白桃系。
◆旬
7月中旬~8月上旬
◆サイズ
大玉。
◆外皮色
白や黄色っぽい。
◆果肉
白。
◆食感・硬さ
とろけるように柔らかい。
◆甘さ
ほどよい甘さ。
◆香り
芳醇な香り。
やまなしはくほう 山梨白鳳
◆産地
山梨県。
◆旬
6月中旬~。
ゆうぞら 夕空
◆歴史
1983年に品種登録。
◆産地
山梨県など。
◆交配
「白桃」と「あかつき」の交配品種。
◆系統
白桃系。
◆旬
8月下旬~。晩生品種。
◆サイズ
大玉。
ゆめあさま 夢あさま
◆歴史
2002年に品種登録。
◆原産
山梨県。山梨県のオリジナル品種。
◆産地
山梨県。
◆旬
7月中旬~。
ゆめかおり
◆産地
山梨県など。
◆旬
9月上旬~下旬。
ゆめみずき 夢みずき
◆歴史
2013年に品種登録。
◆原産
山梨県。山梨県のオリジナル品種。
◆産地
山梨県。
◆交配
大玉の「浅間白桃」と「暁星」の交配品種。
◆名前の由来
「夢のようにみずみずしい桃」からきている。
◆旬
7月中旬~7月下旬
◆サイズ
大玉。
◆外皮色
白でぼかし状の赤が入る
◆甘さ
甘くてジューシー。
桃に近い・似ている果物の種類
ネクタリン
◆大きさ
桃よりもひと回り小さい。
◆外皮色
ツルツルして光沢気味。赤っぽい。見た目はすももなどに近い。
◆果肉色
黄色に近い。
ワッサー
◆産地
長野県須坂市など。
◆交配
白桃とネクタリンの変異種。新しい果物の品種。
◆収穫時期
1種類の収穫時期が1ヶ月くらいという短さの桃と違い、収穫時期は長い。
◆大きさ
桃とネクタリンの間くらいの大きさ。
◆外皮色
桃にそっくり。
◆果肉色
ネクタリンに近く、黄色に近く、赤っぽいスジも入っている。赤黄色い。
◆食感
桃のように柔らかくなく、梨やりんごのように硬い。
◆食べ方
硬い桃を食べる時や、梨やりんごのように、8等分などにして切って食べるとよい。
手に入れたら冷やすのではなく、食べる1時間前に冷蔵庫に入れて冷やして食べるのが一番美味しい。
◆おすすめのレシピ
基本的には、そのまま食べるのが美味しいが、サラダやマリネなどにして食べても美味しい。
桃の収穫体験


山梨県には桃狩りができるところがたくさんあります。現在は、完全予約制のところが多くなっています。特に土日祝日は、必ず予約をしていくようにしましょう。平日でしたら、入れるところもあるかと思います。
収穫体験とはいえ、場所によって「お持ち帰り用収穫体験1個と食べ放題30分」など、いろいろなプランがあるようです。お持ち帰りがなく食べ放題だけのところや、食べ放題の時間が1時間や無限のところや、桃が冷やしてあるところなど、様々です。現地に行く前に事前に「じゃらん遊び体験」などで調査、予約していくのが良いでしょう。

冷たい桃を食べ放題でいただいてきました。
桃の関連記事
◆「花桃」についての記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓









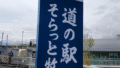
コメント