鶏頭の歴史

鶏頭は、奈良時代に中国を経て渡来しました。
『万葉集』(759年頃編纂・奈良時代末期・歌集)には「からあゐ」という名で登場します。「韓藍(からあゐ)」「辛藍(からあゐ)」「鶏冠草(からあゐ)」という万葉仮名で歌われた歌が4首あり、これは「鶏頭」のことを指しています。この頃、鶏頭の花の汁は、赤くなる塗料に用いられていたことから、情熱的な花の色彩が恋の比喩として表現されていました。
『本草和名(ほんぞうわみょう)』(918年編纂・平安時代・日本最古の本草書)には、「鶏冠草 和名 加良阿為(からあゐ)」とあります。
鶏頭とは

鶏頭の漢名
「鶏頭(けいとう)」
「鶏冠花(けいとうか)」
鶏頭の原産
熱帯アジア、インド。
鶏頭の科属
ヒユ科ケイトウ属。
鶏頭の分類
多年草かと思いがちですが、正しくは1年草です。花が終わる頃にできる種子が飛び散り、毎年同じ場所に咲きます。
鶏頭の名前の由来

花の色と形が、雄鶏(おんどり)の鶏冠(とさか)に似ているから、この名になったとされます。
鶏頭の季語
「秋」になります。
鶏頭の花言葉
「永遠の愛」
「情愛」
「色あせぬ恋」
「おしゃれ」
「個性」
「気取り屋」
ちなみに中国での花言葉は、少し意味が違うようです。
「役人の出世」
「昇進」
鶏頭のエピソード
鶏頭の花と葉は、アフリカや東南アジアでは、食用とされています。日本でも一時期食用とされていた時期はありました。
鶏頭のお花の出生とその姿

鶏頭の草丈
短い約30センチくらいのものから、1メートルほどに長くなるタイプのものもあります。
鶏頭の花について
鶏頭の花は、鶏冠(とさか)部分と思われがちですが、じつは鶏冠部分は花軸の節が石化(帯状化)したものです。柳やエニシダなどの石化柳、石化エニシダなどと同じです。本来の花は、花冠の下部の両側に密集して咲きます。
鶏頭の開花時期
7月上旬から12月頃まで。
鶏頭の花の色
赤、黄色、橙、紫紅、桃色、白などがあります。
鶏頭の花の形
◆トサカ鶏頭
◆久留米鶏頭 くるめけいとう
鶏冠部分がカーネーションのように丸いタイプ。
◆ヤリ鶏頭
◆フサ鶏頭
◆羽毛鶏頭 うもうけいとう
鶏冠部分がふわふわしているタイプ。
鶏頭の種子
種子は光沢のある黒色で小粒です。花が終わる頃に、花の中に見えてきます。
鶏頭の見立て方
鶏頭のいけ方・飾り方のコツ
鶏頭の茎は、とにかく真っ直ぐです。直線的な表現をするにはとても良い花材です。長く大きく使ってあげましょう。
逆に秋に咲く花なのに随分力強く、秋らしく曲線的な表現はできないため、そのような時は短めに使うのが良いでしょう。
鶏頭のいけ方の注意点
鶏頭の茎は、無理に力を入れるとサクっと折れます。茎が丈夫そうだったり、太いからといって気をぬかないようにしましょう。
鶏頭の水揚げ
水揚げもよく、日持ちもするお花です。使い勝手はとても良いです。
鶏頭の切り花の選び方
鶏冠(花冠)部分があまりに大きい場合、全体が大きなお花なら構いませんが、バランスが非常に難しくなります。鶏冠部分を強調する場合は構いませんが、お花全体のバランスをみて、大きさを選ぶと良いでしょう。
鶏頭の品種
鶏頭の園芸品種は、ノゲイトウの改良品種となります。
◆糸鶏頭 いとけいとう
◆ケイトウミックス
初秋から冬にかけて出回る。鶏冠部分が細く軽やか。このタイプは水が下がりやすいので注意。
鶏頭を綺麗に見ることができる場所
◆やまぐちフラワーランド
山口県柳井市。1万本の鶏頭が咲きます。6月下旬~7月上旬までが見頃です。
鶏頭のおすすめの逸品
鶏頭らしくない、グリーンの爽やかな色の鶏頭の苗です。こちらからお取り寄せができます。↓↓↓

お花の関連記事
◆「お花の名前別まとめ(写真付き)」の記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓








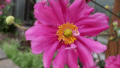
コメント