 8月に咲く花
8月に咲く花 【季節の花図鑑「薊(アザミ)」】アザミ属に属するアザミの仲間たち
アザミ属のお花の魅力として、別名、科属、名前の由来、何年草か、根、葉、つぼみ、開花時期、開花期間、花径、花の色、栽培方法、花言葉、いける・飾る、アザミ属の種類として、フジアザミ、モリアザミ、アザミ属ではないアザミの仲間としてるり玉アザミを紹介
 8月に咲く花
8月に咲く花  1年を通して食べられる和菓子
1年を通して食べられる和菓子  1年を通して食べられる和菓子
1年を通して食べられる和菓子 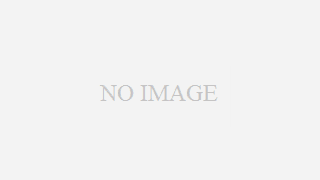 9月にしたい手仕事
9月にしたい手仕事  7月にしたい手仕事
7月にしたい手仕事 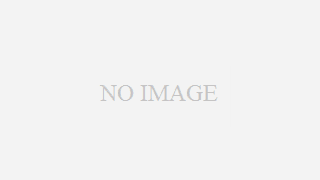 7月にしたい手仕事
7月にしたい手仕事  1年通してしたい手仕事
1年通してしたい手仕事 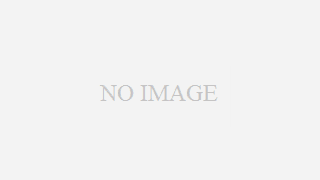 8月にしたい手仕事
8月にしたい手仕事  9月に咲く花
9月に咲く花 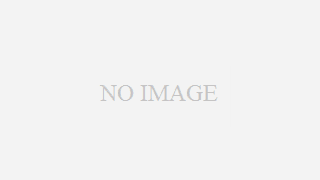 4月にしたい手仕事
4月にしたい手仕事